死亡に関する保険給付
遺族(補償)給付
業務または通勤が原因で亡くなった労働者の遺族に対し、遺族補償給付(業務災害の場合)または遺族給付(通勤災害の場合)が支給されます。残された遺族にとっては死亡という一番悲しい出来事に遭遇してしまい、乱暴な言い方で恐縮ですが、他の保険給付にはない手厚い保険給付となっています。支給額でいうと、先に説明した国民年金は加入期間(保険料納付期間)、そして厚生年金は加入期間と加入期間中の平均年収によって額が決まるしくみですが、労災保険の年金はその方の給料額で決まるしくみとなっています。また、遺族の数で金額も変わります。遺族の数が1人であれば給付基礎日額の153日分(55歳以上か一定の障害の状態にある妻の場合は175日分)、2人であれば201日分、3人であれば223日分となっています。このようなことから、日本の労災年金は世界屈指の手厚さといわれています。
遺族(補償)給付の種類 (法16条)
遺族補償給付は、遺族補償年金又は遺族補償一時金とする。
【遺族給付(法22条の4,1項、2項)】
Ⅰ 遺族給付は、労働者が通勤により死亡した場合に、当該労働者の遺族に対し、その請求に基づいて行なう。
Ⅱ 遺族給付は、遺族年金又は遺族一時金とする。
■遺族(補償)給付の種類
遺族(補償)給付には、遺族(補償)年金,遺族(補償)一時金の2種類があります。
遺族(補償)年金
受給資格者 (法16条の2,1項、2項、(40)法附則43条1項、則14条の4)
Ⅰ 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次のⅰからⅳに掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
ⅰ 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、55歳以上であること。
ⅱ 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
ⅲ 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は55歳以上であること。
ⅳ ⅰからⅲの要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
Ⅱ 労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、Ⅰの規定の適用については、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。
Ⅲ Ⅰに規定する労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたことの認定は、当該労働者との同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項を基礎として厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行う。
【遺族年金の受給資格者(法22条の4,3項、(48)法附則5条1項)】
遺族年金も同様である。
厚生労働省令で定める障害の状態
「厚生労働省令で定める障害の状態」とは、次のいずれかに該当する状態をいう。
① 障害等級の第5級以上に該当する障害がある状態
② 負傷又は疾病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態(少なくとも厚生年金保険の障害等級第2級程度以上の障害の状態に相当する状態)
(則15条、昭和41.1.31基発73号)
生計を維持していた
「生計を維持していた」とは、もっぱら又は主として労働者の収入によって生計を維持されていることを要せず、労働者の収入によって生計の一部を維持されていれば足りる。
したがって、いわゆる共稼ぎもこれに含まれる。 (昭和41.1.31基発73号)
重婚的内縁関係にあった場合の取扱い
被災者が重婚的内縁関係にあった場合の未支給の保険給付、遺族(補償)給付、障害(補償)年金差額一時金の受給権者は、本来、婚姻の成立がその届出により法律上の効力を生ずることとされていることからも、原則として届出による婚姻関係にあった者とするが、届出による婚姻関係がその実体を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消される見込みがなかった場合に限り、事実上の婚姻関係にあった者とする。
(平成10.10.30基発627号)
(労働者の死亡当時生計を維持していた者の取扱い)
労働者の死亡当時における当該遺族の生活水準が年齢、職業等の事情が類似する
一般人のそれをいちじるしく上回る場合を除き、当該遺族が死亡労働者の収入によって消費生活の全部又は一部を営んでいた関係(生計依存関係)が認められる限り、当該遺族と死亡労働者との間に「生計維持関係」があったものと認めて差し支えない。
(昭和41.10.22基発1108号)
受給権者 (法16条の2,3項、(40)法附則43条2項、3項)
遺族(補償)年金は、次に説明する「受給資格者」(受給する資格を有する遺族)のうちの最先順位者(「受給権者」といいます)に対して支給されます。
Ⅰ 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、次の通りとする。
| 順位 | 遺族 | 労働者の死亡当時の要件 |
| 1 | 妻 | |
| 夫 | 60歳以上又は障害の状態にあること | |
| 2 | 子 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある又は障害の状態にあること |
| 3 | 父母 | 60歳以上又は障害の状態にあること |
| 4 | 孫 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある又は障害の状態にあること |
| 5 | 祖父母 | 60歳以上又は障害の状態にあること |
| 6 | 兄弟姉妹 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある若しくは60歳以上又は障害の状態にあること |
| 7 | 夫 | 55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないものである こと |
| 8 | 父母 | |
| 9 | 祖父母 | |
| 10 | 兄弟姉妹 |
(上記1~10のすべてにおいて、労働者の収入によって生計維持していた要件は必要)
Ⅱ Ⅰの7から10までの遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が60歳に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、労働者災害補償保険法附則第60条[遺族補償年金前払一時金]の規定の適用を妨げるものではない。
【遺族年金の受給権者(法22条の4,3項、(48)法附則5条)】
遺族年金も同様である。
転給
遺族(補償)年金の受給権者となるのは、受給資格者のうち最先順位者である。ただし、受給権者が失権し、同順位者がいない場合には次順位者が受給権者となる。
若年支給停止者
順位7から10までの者は、いわゆる「若年支給停止者」といい、受給権者になっても60歳に達するまでは支給が停止されるが、遺族(補償)年金前払一時金を請求することができる。なお、この若年支給停止者が60歳に達しても順位は繰り上がらない。
胎児であった子が生まれた場合の順位
順位3から10までの者が受給権者となっていても、労働者の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは受給権者ではなくなり、胎児であった子が受給権者となる。ただし、失格するわけではないので出生した胎児の受給権が消滅した場合には再び受給権者となることがあり得る。
請求等についての代表者
遺族(補償)年金の受給権者が2人以上あるときは、原則として、そのうち1人を、請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。
(則15条の5,1項、則18条の9,3項)
欠格 (法16条の9,1項、2項、4項、5項)
Ⅰ 労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。
Ⅱ 労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。
Ⅲ 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
Ⅳ Ⅲの欠格事由に該当した場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。
【遺族年金の欠格(法22条の4,3項)】
遺族年金の欠格も同様である。
年金額 (法16条の3,1項、2項、法別表第1、(40)法附則43条1項)
Ⅰ 遺族補償年金の額は、次に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族(55歳以上60歳未満で厚生労働省令で定める障害の状態にない夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹を除く。)の人数の区分に応じ、次に掲げる額とする。
| 遺族の数 | 遺族補償年金の額 |
| 1人 | 給付基礎日額の153日分 ただし、55歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻にあっては、給付基礎日額の175日分 |
| 2人 | 給付基礎日額の201日分 |
| 3人 | 給付基礎日額の223日分 |
| 4人以上 | 給付基礎日額の245日分 |
Ⅱ 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、Ⅰの規定にかかわらず、Ⅰの表に規定する額をその人数で除して得た額とする。
【遺族年金の年金額(法22条の4,3項、(48)法附則5条1項)】
遺族年金の額も同様である。
算定の基礎となる遺族
遺族(補償)年金の額は、受給権者及び受給権者と生計を同じくする受給資格者の人数で決まるが、当該年金額に反映される受給資格者には、55歳以上60歳未満で厚生労働省令で定める障害の状態にない夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹である受給資格者は含まれない(いわゆる若年支給停止者の人数は年金額に反映されない)。
妻の特例
遺族(補償)年金の算定の基礎となる遺族が1人のときの年金額は、原則として給付基礎日額の153日分であるが、当該遺族が55歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻であるときは、給付基礎日額の175日分になる。
年金額の改定 (法16条の3,3項、4項)
Ⅰ 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
Ⅱ 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次のⅰⅱのいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
ⅰ 55歳に達したとき(厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
ⅱ 厚生労働省令で定める障害の状態になり、又はその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)。
【遺族年金の年金額の改定(法22条の4,3項)】
遺族年金の年金額の改定も同様である。
支給停止 (法16条の5、法16条の3,3項)
Ⅰ 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
Ⅱ Ⅰの規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
Ⅲ Ⅰの規定により遺族補償年金の支給が停止され、又はⅡの規定によりその停止が解除されたときは、その支給が停止され、又はその停止が解除された月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
【遺族年金の支給停止(法22条の4,3項)】
遺族年金の支給停止も同様である。
・所在不明による支給停止の解除
支給停止を解除したときは、その解除の月の翌月分から支給を再開すればよく、所在が明らかとなったときにさかのぼる必要はない。
なお、支給停止は申請がない限り行うことができない。 (昭和41.1.31基発73号)
失権及び失格 (法16条の4)
Ⅰ 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次のⅰからⅵのいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。
ⅰ 死亡したとき。
ⅱ 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
ⅲ 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。
ⅳ 離縁によって、死亡した労働者との親族関係が終了したとき。
ⅴ 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
ⅵ 厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については、労働者の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は労働者の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)。
Ⅱ 遺族補償年金を受けることができる遺族がⅠのⅰからⅵのいずれかに該当するに至ったときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。
【遺族年金の失権及び失格(法22条の4,3項)】
遺族年金の失権及び失格も同様である。
失権
遺族(補償)年金の受給権者が上記Ⅰⅰからⅵのいずれかに該当するに至ったときは、その受給権は消滅する。
失格
遺族(補償)年金の受給資格者が上記Ⅰⅰからⅵのいずれかに該当するに至ったときは、その受給資格は消滅する。
直系血族又は直系姻族以外の者の養子
「直系血族又は直系姻族以外の者の養子となる」とは、自己又は自己の配偶者の父母、祖父母等でない者、例えば自己のおじ、おば(傍系親族)その他の者の養子になることをいう。 (昭和41.1.31基発73号)
ご参考(通達)
離縁
「離縁」とは、養子縁組を解消すること、すなわち、養子又は養父母でなくなることをいう。 (同上)
労働者の死亡の当時55歳以上60歳未満で障害の状態にあった者の扱い
労働者の死亡の当時55歳以上60歳未満で障害の状態にあった夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹については、当該障害の状態に該当しなくなったときでも失格しないこととされており、遺族の順位等の規定については、労働者の死亡の当時、「受給権者」の項のⅠの7から10(若年支給停止者)に該当していたものとして扱われる。したがって、当該障害の状態に該当しなくなったときは、遺族の順位は上記7から10に該当することとなる(先順位となるべき者がいれば、順位が入れ替わることとなる。)。
(法附則43条1項、法附則5条1項)




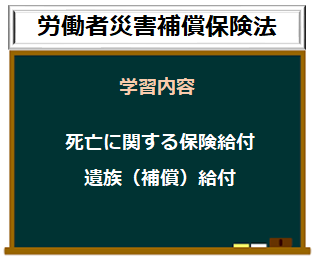
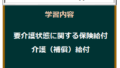
年金前払一時金-120x68.png)