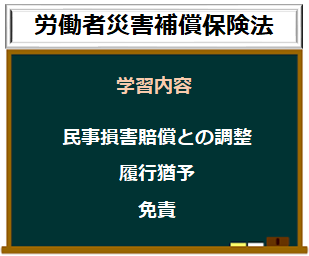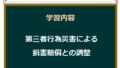民事損害賠償との調整
業務災害又は通勤災害が、事業主の安全配慮義務違反(民法415条)、不法行為(民法709条)、使用者責任(民法715条)、工作物瑕疵(民法717条)等が原因で発生した場合には、事業主に損害賠償を行う義務が発生する。
この場合、被災労働者又はその遺族は、労災保険の保険給付の受給権と事業主からの民事損害賠償請求権を有することになるが、両方の請求権を認めると損害のてん補を二重に受けることになる。また、事業主は、労災保険における保険利益を失うことになる。
このような不合理を避けるため、民事損害賠償と労災保険給付の間で一定の調整が行われる。
民事損害賠償側での調整 (法附則64条1項)
<前提>
労働者又はその遺族が「障害(補償)年金」「遺族(補償)年金」の前払一時金を請求することができる場合に限ります。
履行猶予と免責があります。
①履行猶予
事業主は当該年金の受給権が消滅するまでの間、前払一時金の最高限度額に相当する額(年5分の法定利率を考慮した額)を限度として、損害賠償の履行が猶予される。(履行猶予の措置は事業主側の主張を待って行われる)
②免責
①により履行猶予されている場合は、年金又は前払一時金の支給が現実に行われたときに初めて、事業主はその支給された年金又は前払一時金の額(年5分の法定利率を考慮した額)を限度として、損害賠償の責めを免れる。
詳しく見ていきましょう。
労働者又はその遺族が障害補償年金若しくは遺族補償年金又は障害年金若しくは遺族年金(以下「年金給付」という。)を受けるべき場合(当該年金給付を受ける権利を有することとなった時に、当該年金給付に係る前払一時金給付※を請求することができる場合に限る。)であって、同一の事由について、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から民法その他の法律による損害賠償(当該年金給付によっててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けることができるときは、当該損害賠償については、当分の間、次のⅰ及びⅱに定めるところによるものとする。
※ 障害補償年金前払一時金、遺族補償年金前払一時金、障害年金前払一時金又は遺族年金前払一時金をいう。
ⅰ 事業主は、当該労働者又はその遺族の年金給付を受ける権利が消滅するまでの間、その損害の発生時から当該年金給付に係る前払一時金給付を受けるべき時までの法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該前払一時金給付の最高限度額に相当する額となるべき額(ⅱの規定により損害賠償の責めを免れたときは、その免れた額を控除した額)の限度で、その損害賠償の履行をしないことができる。
ⅱ ⅰの規定により損害賠償の履行が猶予されている場合において、年金給付又は前払一時金給付の支給が行われたときは、事業主は、その損害の発生時から当該支給が行われた時までの法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該年金給付又は前払一時金給付の額となるべき額の限度で、その損害賠償の責めを免れる。
履行猶予・免責
前払一時金給付を請求することができる障害(補償)年金又は遺族(補償)年金の受給権者が、同一の事由について、事業主からこれらの年金給付に相当する民事損害賠償を受けることができるときは、まず、その事業主は、これらの者の年金受給権が消滅するまでの間、前払一時金給付の最高限度額の法定利率による現価の限度で、損害賠償の履行が猶予され、そして、年金受給権者に労災保険から年金給付又は前払一時金給付が支給される都度、その支給額の法定利率による現価の限度で損害賠償の責任が免除される(免責)。
⑴ 履行猶予額
損害賠償の履行猶予額は次のように算定する。
履行猶予額 = 前払一時金給付の最高限度額 -
損害発生時から前払一時金を受けるべき時までの期間につき年5分で計算される額
⑵ 免責額
損害賠償の免責額は次のように算定する。
免責額 = 年金給付又は前払一時金給付の支給額 -
損害発生時から年金又は前払一時金を受けた時までの期間につき年5分で計算される額
調整の範囲
慰謝料、物的損害等が調整の対象とされないのは、第三者行為災害の場合と同様である。当該調整対象となる損害賠償額は、年金給付によっててん補される部分に限るので、労災保険の年金給付のてん補対象となる部分を超えて行われた損害賠償部分(上積分)は当該調整の対象とならない。また、既支給の年金給付によって既にてん補された部分も当該調整の対象とならない。 (昭和56.10.30基発696号)
判例
(労災保険給付と損害賠償との調整)
結論:使用者が賠償すべき損害額から、将来支給予定の年金給付分は控除できない。
政府が保険給付をしたことによって、受給権者の使用者に対する損害賠償請求権が失われるのは、右保険給付が損害の填補の性質をも有する以上、政府が現実に保険金を給付して損害を填補したときに限られ、いまだ現実の給付がない以上、たとえ将来にわたり継続して給付されることが確定していても、受給権者は使用者に対し損害賠償の請求をするにあたり、このような将来の給付額を損害賠償債権額から控除することを要しないと解するのが、相当である。(最三小昭和52.10.25三共自動車事件)
(損益相殺的調整の対象となる損害)
結論:損害賠償額から労災給付分を相殺するときは、賠償額の「元本」との間で損益相殺的な調整を行う。
労働者が使用者の不法行為によって死亡し、その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受けることが確定したときは、損害賠償額を算定するにあたり、当該遺族補償年金の填補の対象となる損害は、特段の事情のない限り、不法行為の時に填補されたものと法的に評価して、損益相殺的な調整をすることが相当である。 (最大判平成27.3.4フォーカスシステムズ労災遺族年金事件)
前払一時金給付を請求することができる場合
先順位の受給権者が前払一時金を受けた後に失権することにより遺族(補償)年金の受給権者となった者のように前払一時金給付を請求できない者については、「受給権を取得したときに前払一時金給付を請求することができる場合」に該当しないため、当該調整規定は適用されません。(転給者は適用されない)
一方、損害賠償を請求し、その損害賠償額を算定する時点で時効等により前払一時金給付の権利行使の制限期間を徒過しているために前払一時金給付を請求できないだけであるときは、「受給権を取得したときに前払一時金給付を請求することができる場合」に該当するので、当該調整規定が適用されます。
労災保険給付側での調整 (法附則64条2項)
損害賠償が先行して行われた場合の調整です。
同一事由について労働者又はその遺族が、事業主から損害賠償を受けたときは、政府は労働政策審議会の議を経て厚生労働大臣が定める基準により、その価格の限度で、保険給付を行わないことができる。
労働者又はその遺族が、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から損害賠償を受けることができる場合であって、保険給付を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償(当該保険給付によっててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けたときは、政府は、労働政策審議会の議を経て厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。ただし、前項に規定する年金給付[民事損害賠償側での調整の規定により前払一時金給付を請求することができる場合の年金給付]を受けるべき場合において、次に掲げる保険給付については、この限りでない。ⅰ 年金給付〔労働者又はその遺族に対して、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該年金給付に係る前払一時金給付の最高限度額(当該前払一時金給付の支給を受けたことがある者にあっては、当該支給を受けた額を控除した額とする。)に相当する額に達するまでの間についての年金給付に限る。〕
ⅱ 障害補償年金差額一時金及び第16条の6第1項第2号の場合[遺族補償年金の受給権者が全員失権した場合]に支給される遺族補償一時金並びに障害年金差額一時金及び第22条の4第3項において読み替えて準用する第16条の6第1項第2号の場合[遺族年金の受給権者が全員失権した場合]に支給される遺族一時金
ⅲ 前払一時金給付
調整対象
労働者又はその遺族が事業主から保険給付の事由と同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。
ただし、当該労働者等が前払一時金給付を請求することができる年金給付を受けるべき場合においては、前払一時金給付の最高限度額に達するまでの年金給付〔各月に支給される年金給付の額の合算においては、最初の年金給付の支払期月から1年経過月以後の分は年5分の単利で割り引いて合算する。また、各月に支給される年金給付のほか、障害(補償)年金差額一時金、遺族(補償)年金の受給権者が全員失権した場合に支給される遺族(補償)一時金又は前払一時金給付として支給される部分を含む。〕については損害賠償を受けても支給調整(控除)されない。 (則附則44項)
労災保険給付の支給調整基準
事業主から損害賠償が行われた場合の労災保険給付の支給調整基準について、主なものをあげると以下の通りである。
⑴ 労災保険の給付に上積みして支給される企業内労災補償、示談金、和解金、見舞
金等については、原則として調整対象としない。
⑵ 転給により受給権を取得した者については、支給調整は行わない。
⑶ 調整対象となる損害賠償額には、受給権者本人以外の遺族が受けた損害賠償額は含まれない。 (昭和56.6.12発基60号、昭和56.10.30基発696号)
支給調整期間
支給調整は、次の期間を限度として行われる。
⑴ 障害(補償)年金及び遺族(補償)年金は、前払一時金の最高限度額に相当する額の年金が支給される期間が満了する月から起算して9年が経過するまでの期間
⑵ 傷病(補償)年金は、年金の支給事由が発生した月の翌月から起算して9年が経過するまでの期間
⑶ 休業(補償)給付は、災害発生日から起算して9年が経過するまでの期間
⑷ 就労可能年齢※を超えるに至ったときは、その超えるに至ったときまでの期間
※ 「就労可能年齢」は、被災した際の年齢別に定められている。
【例 】70歳で被災した労働者の就労可能年数は6年(76歳まで働ける)とされている。
(平成5.3.26発基29号)
調整の範囲
保険給付の支給調整の対象となる民事損害賠償の損害項目は、逸失利益(災害がな
ければ稼働して得られたであろう賃金分)、療養費、葬祭費用並びに介護損害である
判例
(「同一の事由」の意義)
結論:労災保険の保険給付と積極的財産損害(入院雑費、付添看護費等)及び精神的損害(慰謝料)との間で支給調整を行うことはできない。
政府が被災労働者に対し労災保険法に基づく保険給付をしたときは、当該労働者の使用者に対する損害賠償請求権は、その保険給付と同一の事由については損害の填補がされたものとしてその給付の価額の限度において減縮するが、同一の事由の関係にあることを肯定できるのは、財産的損害のうちの消極損害(いわゆる逸失利益)のみであり、保険給付が消極損害の額を上回るとしても、当該超過分を、財産的損害のうちの積極損害(入院雑費、付添看護費を含む。)及び精神的損害(慰謝料)を填補するものとして、これらとの関係で控除することは許されない。(最二小昭和62.7.10青木鉛鉄事件)
「 民事損害賠償側での調整」の規定により猶予・免責が行われるのは、将来分の一定部分について一括一時金で確実に給付が行われる場合〔前払一時金制度のある年金給付である遺族(補償)年金又は障害(補償)年金を受けることができる場合〕に限られるが、 「労災保険給付側での調整」の規定による控除においては、重複てん補を回避するための調整規定として、保険給付の種類を限定していない。