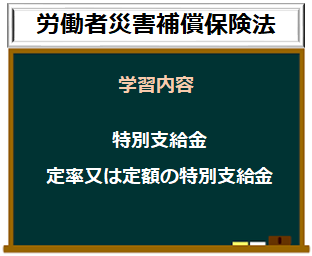特別支給金
特別支給金は、社会復帰促進等事業の1つで労災保険の給付に付加して支給を行うものです。
種類等
特別支給金とは、保険給付に上乗せして支給される金銭給付であり、次の2つに大別されます。
◆定率又は定額の特別支給金
◆特別給与を算定基礎とする特別支給金
特別支給金と保険給付の関係をまとめると以下のようになる。
| 特別給与を算定基礎とする特別支給金 | |||||
| 傷病 特別年金 | 障害 特別年金 | 障害 特別一時金 | 遺族 特別年金 | 遺族 特別一時金 | |
定率又は定額の特別支給金 | |||||
| 休業 特別支給金 (定率支給) | 傷病 特別支給金 (定額支給) | 障害特別支給金 (定額支給) | 遺族特別支給金 (定額支給) | ||
| 休業 (補償) 給付 | 傷病 (補償) 年金 | 障害 (補償) 年金 | 障害 (補償) 一時金 | 遺族 (補償) 年金 | 遺族 (補償) 一時金 |
定率又は定額の特別支給金
休業特別支給金 (支給金則3条1項)
支給額
⑴ 原則
休業特別支給金の支給額は、休業給付基礎日額の100分の20に相当する額である。
したがって、被災労働者は、休業(補償)給付と合わせて給付基礎日額の80%相当額が補償されることになります。
| 休業特別支給金 給付基礎日額の20%相当額 |
| 休業(補償)給付 給付基礎日額の60%相当額 |
⑵ 一部労働の場合
一部労働の場合は、休業給付基礎日額から賃金額を控除した額の20%が支給額となる〔休業(補償)給付と同様である。〕。 (支給金則3条1項)
⑶ 刑事施設拘禁等の場合
刑事施設及び少年院等に拘禁又は収容された場合には、原則として、休業特別支給金は支給されない〔休業(補償)給付と同様である。〕。 (支給金則3条2項)
申請等
⑴ 申請
休業特別支給金の支給の対象となる日について休業(補償)給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該休業(補償)給付の請求と同時に行わなければならない。 (支給金則3条5項)
⑵ 特別給与の総額の届出
休業特別支給金の支給の申請の際に、特別給与の総額について、事業主の証明を受けたうえで、これを記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないこととされている。 (支給金則12条)
(特別給与の総額の届出)
特別給与を算定基礎とする特別支給金の算定に必要な特別給与の総額の届出は休業特別支給金の支給の申請の際に行うこととされている。この届出をしておけば、以後は当該届出をする必要がなく、障害特別年金、障害特別一時金又は傷病特別年金の支給の申請を行う場合及び遺族が遺族特別年金又は遺族特別一時金の支給の申請を行う場合には、申請書記載事項のうち、特別給与の総額については記載する必要がないものとして取り扱われる。 (昭和56.7.4基発415号)
傷病特別支給金 (支給金則5条の2,1項、同則別表第1の2)
傷病特別支給金は、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次のⅰⅱのいずれにも該当するとき、又は同日後次のⅰⅱのいずれにも該当することとなったときに、当該労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、次表に規定する額とする。
ⅰ 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
ⅱ 当該負傷又は疾病による障害の程度が傷病等級に該当すること。
| 傷病等級 | 額 |
| 第1級 | 114万円 |
| 第2級 | 107万円 |
| 第3級 | 100万円 |
支給額
傷病特別支給金の支給額は、傷病等級に応じて114万円、107万円、100万円である。
| 傷病特別支給金 (114万円~100万円) |
| 傷病(補償)年金 給付基礎日額の313日~245日分 |
申請等
傷病特別支給金の申請については、当分の間、事務処理の便宜を考慮し、傷病(補償)年金の支給決定を受けた者は、傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱って差し支えない。 (昭和56.6.27基発393号)
障害特別支給金 (支給金則4条1項、同則別表第1)
障害特別支給金は、業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病が治ったとき身体に障害がある労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、次表に規定する額とする。
| 障害等級 | 額 | 障害等級 | 額 |
| 第1級 | 342万円 | 第8級 | 65万円 |
| 第2級 | 320万円 | 第9級 | 50万円 |
| 第3級 | 300万円 | 第10級 | 39万円 |
| 第4級 | 264万円 | 第11級 | 29万円 |
| 第5級 | 225万円 | 第12級 | 20万円 |
| 第6級 | 192万円 | 第13級 | 14万円 |
| 第7級 | 159万円 | 第14級 | 8万円 |
第1級~第14級の等級に応じ、342万円から8万円の範囲内と覚えておけばよい。
支給額
⑴ 原則
障害特別支給金の支給額は、上記の表の通りである。障害(補償)給付の場合は、障害等級が第1級から第7級のときは年金が支給されるが、障害特別支給金の場合、障害等級が第1級から第7級のときも一時金として支給される。
| 障害特別支給金 342万円~159万円 |
| 障害(補償)年金 給付基礎日額の313日~131日分 |
障害特別支給金 65万円~8万円 |
障害(補償)一時金 給付基礎日額の503日~56日分 |
⑵ 併合繰上げが行われた場合
併合繰上げが行われた場合に、各々の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額の合算額が、併合繰上げされた障害等級に応ずる障害特別支給金の額に満たないときは、当該合算額とする。
【例 】第9級(50万円)と第13級(14万円)の障害を同時に残した場合は、併合繰上げにより第8級(65万円)となるが、支給額は50万円+14万円=64万円となる。
(支給金則4条1項)
⑶ 加重障害・再発治ゆの場合
加重障害や再発治ゆの場合は、差額支給となる(加重後又は再発治ゆ後の障害等級に応ずる額から従前の障害等級に応ずる額を差し引いた額となる)。
【例 】第11級(29万円)の障害を有していた者が加重により第7級(159万円)に該当した場合には、159万円-29万円=130万円が支給される。
(支給金則4条2項)
障害特別支給金は一時金なので、変更により新たに他の障害等級に該当するに至ったとしても、その障害等級に応ずる障害特別支給金は支給されない。(昭和55.12.5基発673号)
申請等
同一の事由により障害(補償)給付の支給を受けることができる者は、障害特別支給金の支給の申請を、当該障害(補償)給付の請求と同時に行わなければならない。
(支給金則4条7項)
遺族特別支給金 (支給金則5条1項、2項、3項)
Ⅰ 遺族特別支給金は、業務上の事由又は通勤により労働者が死亡した場合に、当該労働者の遺族に対し、その申請に基づいて支給する。
Ⅱ 遺族特別支給金の支給を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とし、これらの遺族の遺族特別支給金の支給を受けるべき順位は、遺族補償給付又は遺族給付の例による。
Ⅲ 遺族特別支給金の額は、300万円(当該遺族特別支給金の支給を受ける遺族が2人以上ある場合には、300万円をその人数で除して得た額)とする。
支給額
遺族特別支給金の支給額は、300万円(原則)である。
なお、遺族特別支給金は、遺族(補償)年金又は遺族(補償)一時金の受給権者に支給されるが、転給により遺族(補償)年金の受給権者となった者や全員失権により遺族(補償)一時金(いわゆる失権差額一時金)の受給権者となった者には支給されない。
遺族特別支給金※1 (300万円) |
遺族(補償)年金 給付基礎日額の245日~153日分 |
※1 転給により遺族(補償)年金の受給権者となった者には、支給されない。
遺族特別支給金※2 (300万円) |
遺族(補償)一時金 給付基礎日額の1,000日分 - 既受給額 |
※2 失権差額一時金を受給する者には支給されない。
申請等
同一の事由により遺族(補償)給付の支給を受けることができる者は、遺族特別支給金の支給の申請を、当該遺族(補償)給付の請求と同時に行わなければならない。
(支給金則5条7項)