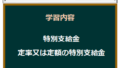特別給与を算定基礎とする特別支給金
特別給与(ボーナス等)を算定の基礎とする特別支給金について解説していきます。
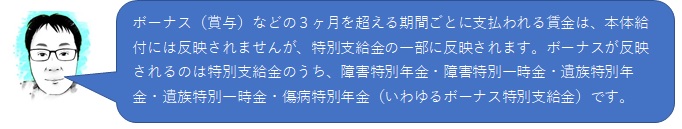
特別給与(ボーナス等)を算定の基礎とする特別支給金には、傷病特別年金、障害特別年金、障害特別一時金、障害特別年金差額一時金、遺族特別年金、遺族特別一時金があります。
算定基礎年額及び算定基礎日額 (支給金則6条1項、2項、4項~6項)
- 特別給与を算定基礎とする特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間(雇入後1年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第12条第4項の3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。)の総額とする。ただし、当該特別給与の総額を算定基礎年額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算定する額を算定基礎年額とする。
- 特別給与の総額又は1ただし書[厚生労働省労働基準局長が定める基準による算定]に定めるところによって算定された額が、当該労働者に係る給付基礎日額に365を乗じて得た額の100分の20に相当する額を超える場合には、当該100分の20に相当する額を算定基礎年額とする。
- 1、2の規定によって算定された額[算定基礎年額として算定された額]が150万円を超える場合には、150万円を算定基礎年額とする。
- 特別給与を算定基礎とする特別支給金の額の算定に用いる算定基礎日額は、1、2,3の算定基礎年額を365で除して得た額を当該特別支給金に係る法の規定による保険給付の額の算定に用いる給付基礎日額とみなして法第8条の3第1項[年金給付基礎日額のスライド改定]の規定の例により算定して得た額とする。
- 算定基礎年額又は算定基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。
算定基礎年額の算定
下記(1)~(3)で、最も低い額を算定基礎年額とします。
(1)負傷又は発病の日以前1年間の特別給与の総額
(2)給付基礎日額に365を乗じて得た額の20%相当額
(3)150万円
特別給与を算定基礎とする特別支給金の額の算定には算定基礎日額が用いられるが、当該日額は、算定基礎年額〔特別給与(賞与)の年額〕を365で除すことによって算出されます。
算定基礎年額は、原則として、負傷又は発病の日以前1年間(雇入後1年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金)の総額ですが、その上限は、「給付基礎日額に365を乗じて得た額の20%相当額」又は「150万円」のいずれか低い方の額とされています。したがって、⑴から⑶の額のうち最も低い額が算定基礎年額となります。
算定基礎日額の算式
算定基礎日額=算定基礎年額÷365(1円未満切上げ)
傷病特別年金 (支給金則11条1項、同則別表第2)
傷病特別年金は、法の規定による傷病補償年金又は傷病年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該傷病補償年金又は傷病年金に係る傷病等級に応じ、次表に規定する額とする。
| 傷病等級 | 年金額 |
| 第1級 | 算定基礎日額の313日分 |
| 第2級 | 算定基礎日額の277日分 |
| 第3級 | 算定基礎日額の245日分 |
支給額
傷病特別年金の支給額は、傷病等級に応じて算定基礎日額の313日分から245日分です。
申請等
傷病特別年金の支給申請については、当分の間、休業特別支給金の支給の申請の際に特別給与の総額についての届出を行っていない者を除き、事務処理の便宜を考慮し、傷病(補償)年金の支給決定を受けた者は、所定の申請を行ったものとして取り扱って差し支えないとされている。(昭和56.7.4基発415号)
障害特別年金 (支給金則7条1項、同則別表第2)
障害特別年金は、法の規定による障害補償年金又は障害年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害補償年金又は障害年金に係る障害等級に応じ、次表に規定する額とする。
| 障害等級 | 年金額 |
| 第1級 | 算定基礎日額の313日分 |
| 第2級 | 算定基礎日額の277日分 |
| 第3級 | 算定基礎日額の245日分 |
| 第4級 | 算定基礎日額の213日分 |
| 第5級 | 算定基礎日額の184日分 |
| 第6級 | 算定基礎日額の156日分 |
| 第7級 | 算定基礎日額の131日分 |
支給額
⑴ 原則
障害特別年金の支給額は、障害等級に応じて算定基礎日額の313日分から131日分です。
⑵ 加重等の取扱い
加重、変更、再発治ゆの場合の取扱いは障害(補償)年金と同様です。(支給金則7条2項、5項)
申請等
障害特別年金の支給の申請は、障害(補償)年金の請求と同時に行わなければならない。 (支給金則7条7項)
障害特別一時金 (支給金則8条1項、同則別表第3)
障害特別一時金は、法の規定による障害補償一時金又は障害一時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害補償一時金又は障害一時金に係る障害等級に応じ、次表に規定する額とする。
| 障害等級 | 年金額 |
| 第8級 | 算定基礎日額の503日分 |
| 第9級 | 算定基礎日額の391日分 |
| 第10級 | 算定基礎日額の302日分 |
| 第11級 | 算定基礎日額の223日分 |
| 第12級 | 算定基礎日額の156日分 |
| 第13級 | 算定基礎日額の101日分 |
| 第14級 | 算定基礎日額の56日分 |
支給額
⑴ 原則
障害特別一時金の支給額は、障害等級に応じて算定基礎日額の503日分から56日分です。
⑵ 併合繰上げが行われた場合
併合繰上げが行われた場合に、各々の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別一時金の額の合算額が、併合繰上げされた障害等級に応ずる障害特別一時金の額に満たないときは、当該合算額とします。
【例 】第9級(391日分)と第13級(101日分)の障害を同時に残した場合は、併合繰上げにより第8級(503日分)となるが、支給額は391日分+101日分=492日分となります。 (支給金則8条1項)
⑶ 加重等の場合
加重障害や再発治ゆの場合は、差額支給となる。 (支給金則8条2項)
申請等
障害特別一時金の支給の申請は、障害(補償)一時金の請求と同時に行わなければならない。 (支給金則8条2項)
障害特別年金差額一時金 (支給金則附則6項)
障害特別年金差額一時金は、当分の間、この省令の規定による特別支給金として、法の規定による障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、次表に規定する額から当該労働者の障害に関し支給された障害特別年金の額の合計額を差し引いた額とする。
| 障害等級 | 額 |
| 第1級 | 算定基礎日額の1,340日分 |
| 第2級 | 算定基礎日額の1,190日分 |
| 第3級 | 算定基礎日額の1,050日分 |
| 第4級 | 算定基礎日額の920日分 |
| 第5級 | 算定基礎日額の790日分 |
| 第6級 | 算定基礎日額の670日分 |
| 第7級 | 算定基礎日額の560日分 |
支給額
障害特別年金差額一時金の支給額は、障害等級に応じた限度額から既に受給した障害特別年金の額の合計額を控除した額です。
申請等
障害特別年金差額一時金の支給の申請は、障害(補償)年金差額一時金の請求と同時に行わなければならない。 (支給金則附則9項)
遺族特別年金 (支給金則9条1項、同則別表第2)
遺族特別年金は、法の規定による遺族補償年金又は遺族年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、次のⅰからⅳに掲げる法の規定による遺族補償年金又は遺族年金の受給権者及びその者と生計を同じくしている法の規定による遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族(55歳以上60歳未満で厚生労働省令で定める障害の状態にない夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹を除く。)の人数の区分に応じ、ⅰからⅳに掲げる額とする。
- 1人 算定基礎日額の153日分。ただし、55歳以上の妻又は労災則第15条に規定する障害の状態にある妻にあっては、算定基礎日額の175日分とする。
- 2人 算定基礎日額の201日分
- 3人 算定基礎日額の223日分
- 4人以上 算定基礎日額の245日分
支給額
遺族特別年金の支給額は、遺族(補償)年金の支給額の算定の対象となる遺族の数に
応じて算定基礎日額の245日分から153日分である。
申請等
遺族特別年金の支給の申請は、遺族(補償)年金の請求と同時に行わなければならな
い。 (支給金則9条7項)
・ 遺族(補償)年金のいわゆる若年支給停止期間中は、遺族特別年金の支給も停止される。 (同上)
・ 所在不明の場合には、遺族特別年金も支給停止の対象となる。 (同上)
遺族特別一時金 (支給金則10条1項、同則別表第3)
ⅰ 労働者の死亡の当時遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族がないときの遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者の場合は、算定基礎日額の1,000日分
ⅱ 遺族補償年金又は遺族年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額の合計額又は遺族年金及び遺族年金前払一時金の額の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たないときの遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者の場合は、算定基礎日額の1,000日分から当該労働者の死亡に関し支給された遺族特別年金の額の合計額を控除した額
支給額
遺族特別一時金の支給額は、算定基礎日額の1,000日分から既に受給した遺族特別年金の額を控除した額です。
申請等
遺族特別一時金の支給の申請は、遺族(補償)一時金の請求と同時に行わなければならない。 (支給金則10条4項)
特別支給金の通則事項
申請手続
特別支給金は全て、所轄労働基準監督署長に「申請」することによって支給決定されます。
当該申請は原則として保険給付の「請求」と同時に行わなければなりません。ただし、傷病特別支給金、傷病特別年金及び差額支給金の申請は、傷病(補償)年金が、「職権」によって支給決定されるため、法律上は独自に申請を行うことになります。
申請期限
特別支給金の申請期限は次の通りです。
| 特別支給金 | 起算日 | 申請期限 |
| 休業特別支給金 | 休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日 | 2年以内 |
| 傷病特別支給金 | 療養開始後1年6箇月経過日又は同日後支給 要件に該当することとなった日の翌日 | 5年以内 |
| 障害特別支給金 | 傷病が治ゆした日の翌日 | |
| 遺族特別支給金 | 労働者死亡日の翌日 | |
| 傷病特別年金及び差額支給金 | 傷病(補償)年金の受給権者となった日の翌日 | |
| 障害特別年金 | 障害(補償)年金の受給権者となった日の翌日 | |
| 障害特別一時金 | 障害(補償)一時金の受給権者となった日の翌日 | |
| 障害特別年金差額一時金 | 障害(補償)年金差額一時金の受給権者となった日の翌日 | |
| 遺族特別年金 | 遺族(補償)年金の受給権者となった日の翌日 | |
| 遺族特別一時金 | 遺族(補償)一時金の受給権者となった日の翌日 |
スライド
特別支給金に係るスライド改定は次の通りである。
⑴ 休業特別支給金については、その算定基礎が休業(補償)給付と同じ休業給付基礎日額であるので、休業(補償)給付と同様のスライド改定が行われることになる。
(支給金則3条1項)
⑵ 傷病特別支給金、障害特別支給金及び遺族特別支給金は、定額制であるのでスライド制の適用はない。
⑶ 特別給与を算定基礎とする特別支給金は、その算定基礎となる算定基礎日額が、年金給付基礎日額と同様のスライドの適用を受ける(年金たる保険給付と同様のスライド改定となる。)。
特別支給金と保険給付の相違点
| 保険給付 | 特別支給金 | |
| 事業主からの費用徴収 | 費用徴収の対象となる | 費用徴収の対象とならない |
| 不正受給者からの費用徴収 | 費用徴収の対象となる | 費用徴収の対象とならない |
| 第三者行為災害による損害賠償との調整 | 行われる | 行われない |
| 事業主から損害賠償を受けることができる場合の調整 | 行われる | 行われない |
| 社会保険との併給調整 | 行われる | 行われない |
| 譲渡・差押えの禁止 | 譲渡・差押え等は禁止されている | 譲渡・差押え等は禁止されていない |
| 法38条1項の不服申立 | 対象となる | 対象とならない |
判例
(損害賠償からの労災特別支給金の控除)
政府が被災労働者に支給する特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として、被災労働者の療養生活の援護等によりその福祉の増進を図るために行われるものであり、被災労働者の損害を填補する性質を有するということはできず、したがって、被災労働者の受領した特別支給金を、使用者又は第三者が被災労働者に対し損害賠償すべき損害額から控除することはできない。
特別支給金と保険給付の主な類似点
⑴ 支給制限及び一時差止めの対象となる。 (支給金則20条)
⑵ 年金たる特別支給金の端数処理、支払時期等は年金たる保険給付と同様の取扱いである。 (支給金則13条他)
⑶ 支払の調整(内払・充当)の対象となる。 (支給金則14条、14条の2)
⑷ 未支給の特別支給金を申請することができる(未支給の保険給付の請求と同時に申請しなければならない。)。 (支給金則15条)
⑸ 公課の禁止、退職後の権利が運用上認められている。
⑹ 船舶事故等の場合には死亡の推定の対象となる。 (支給金則5条9項)