社会復帰促進等事業の種類 (法29条1項、3項)
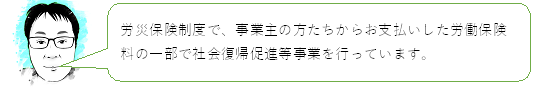
Ⅰ 政府は、労働者災害補償保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。
- 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害及び通勤災害を被った労働者(以下「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
- 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業
- 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業
Ⅱ 政府は、Ⅰの社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康安全機構法に掲げるものを独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとする。
■社会復帰促進等事業
労災保険制度で、事業主の方たちからお支払いした労働保険料の一部で、以下の3つの事業を行うもの。
・社会復帰促進事業(労災病院の設置・運営等)
被災労働者の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
・被災労働者等援護事業(特別支給金の支給等)
被災労働者とその遺族の援護を図るために必要な事業
・安全衛生確保等事業(未払賃金の立替払事業等)
労働者の安全と衛生の確保などのために必要な事業
独立行政法人労働者健康安全機構は、次のような業務等を行っています。
独立行政法人労働者健康安全機構は、厚生労働省所管の独立行政法人です。
(業務の範囲)
①労災病院等の療養施設の設置・運営を行うこと。
②労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置・運営を行うこと。
③事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究を行うこと(④に掲げるものを除く。)
④化学物質で労働者の健康障害を生ずるおそれのあるものの有害性の調査を行うこと
⑤前2号(③④)に掲げる業務に係る成果を普及すること
⑥賃金の支払の確保等に関する法律第3章に規定する事業(同法第8条に規定する業務を除く。)を実施すること。
未払賃金の立替払
⑦被災労働者に係る納骨堂の設置・運営を行うこと。
等 (独立行政法人労働者健康安全機構法12条1項)
・特別支給金、労災就学援護費、労災就労保育援護費、休業補償特別援護金の支給の事務は所轄労働基準監督署長が行う。( 昭和57.5.26基発361号)
・社会復帰促進等事業は、政府が統括して行うが、その一部については、独立行政法人労働者健康安全機構が行っている。
社会復帰促進事業
被災労働者の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業として、例えば以下のような事業が行われている。
⑴ 労災病院等の設置・運営
社会復帰促進事業として、労災病院※等の設置・運営が行われている。
※「労災病院」とは、労働災害による一般診療の他、外科後処置、義肢補装具の支給、リハビリテーション等の指導も行う施設であり、独立行政法人労働者健康安全機構が設置・運営する。
⑵ 外科後処置等
社会復帰促進事業として、義肢装着のための再手術等の外科後処置※、義肢や義眼等の補装具の支給、これらに係る旅費の支給等も行われている。
※外科後処置」とは、傷病が治ゆした後において行う義肢装着のための再手術、顔面醜状の整形手術、理学療法等をいい、労災病院のほか国立病院等でも行われている。
⑶ アフターケア
業務災害又は通勤災害により、せき髄損傷、頭頸部外傷症候群、慢性肝炎、振動障害等の傷病にり患した者については、その症状が固定した後においても後遺症状に動揺をきたす場合や後遺障害に付随する疾病を発症する場合があることから、20傷病について、必要に応じ予防その他の保健上の措置として診察、保健指導、検査などを実施するものである。〈発展16.参照〉
被災労働者等援護事業
被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業として、例えば以下のような事業が行われている。
⑴ 特別支給金の支給
⑵ 労災就学援護費
被災労働者やその子弟又はその遺族の学費の援助をする制度であり、在学者の区分に応じ、在学者1人につき一定額を支給するものである。なお、労災就学援護費は、他の育英制度による奨学金と異なり、返還を要しない。また、他の奨学金制度の奨学金を受けても減額されない。 (昭和45.10.27基発774号、平成29.3.31基発0331第65号)
① 支給対象者
労災就学援護費の支給を受ける者は、在学している年金受給権者〔障害(補償)年金の場合は障害等級3級以上の年金受給権者〕、又は、被災労働者の子であって在学している者と同一生計にある年金受給権者である。
なお、労災就学援護費は業務災害による年金の受給権者に限らず、通勤災害による年金の受給権者に対しても支給される。
② 欠格事由
労災就学援護費に係る在学者等が次のいずれかに該当した場合には、その該当月の翌月以降原則として、労災就学援護費の支給は行われない。
ア 婚姻をしたとき
イ 直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったとき
ウ 離縁によって死亡した労働者との親族関係が終了したとき
判例
(労災就学援護費不支給決定の処分性)
労働基準監督署長の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者又はその遺族の権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものと解するのが相当である。(最一小平成15.9.4中央労基署長(労災就学援護費)事件)
⑶ 労災就労保育援護費
被災労働者やその子弟又はその遺族の保育費の援助をする制度であり、支給要件、欠格事由、手続等は、労災就学援護費の場合とほぼ同様である。
(昭和54.4.4基発160号、平成29.3.31基発0331第65号)
⑷ 休業補償特別援護金
事業場廃止等により労働基準法の規定による待期期間中の休業補償を受けることができない労働者に対して、休業補償給付の3日分を支給する制度である。
(平成25.5.31基発0531第3号)
⑸ 年金担保資金貸付制度
年金受給権を担保として、独立行政法人福祉医療機構が小口資金の貸付をする制度である。 (独立行政法人福祉医療機構法12条1項13号)
安全衛生確保等事業
安全衛生確保等事業として、事業主に対する労働災害の防止に関する啓蒙指導(講習会、パンフ配布等)、労働災害防止協会に対する補助金の支給や労働者の未払賃金につき、一定範囲内において国が事業主に代わって立替払を行う未払賃金の立替払事業が行われています。
未払賃金の立替払事業は、労災保険の適用事業の労働者を対象として行われるので、労災保険の暫定任意適用事業で労災保険に加入手続を取っていない事業の労働者は対象外である





