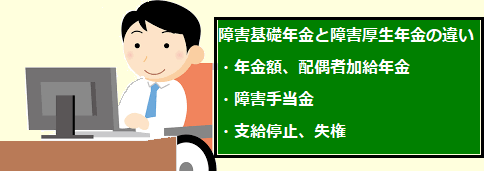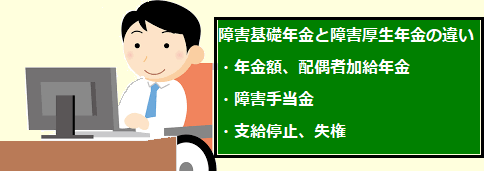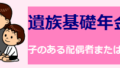今回は、障害厚生年金の年金額、65歳未満の配偶者がいる場合の加算額、障害厚生年金独自の障害手当金、支給停止要件、失権に関する規定を解説します。
障害厚生年金の年金額
厚生年金保険は報酬比例の年金ですから、障害厚生年金の額も「老齢厚生年金の規定の例により計算した額」とされ、報酬に比例します。
障害基礎年金と同様に2級を基準とし、1級はその1.25倍です。
①1,000分の7.125や1,000分の5.481の支給乗率は、生年月日にかかわらず定率です。
(本来水準)
障害年金においては経過措置を設ける必要がないためです。昭和61年4月の改正を境
に、一気に年金額を減らしました。
年金額は、平成15年4月1日前の被保険者期間と平成15年4月1日以後の被保険者期間を
合算した額です。
平成15年4月1日前の被保険者期間についての年金額
1級
平均標準報酬月額(再評価)×7.125/1,000×被保険者期間の月数×1.25+配偶者加給年金額
2級
平均標準報酬月額(再評価)×7.125/1,000×被保険者期間の月数+配偶者加給年金額
3級
平均標準報酬月額(再評価)×7.125/1,000×被保険者期間の月数
平成15年4月1日以後の被保険者期間についての年金額
1級
平均標準報酬額(再評価)×5.481/1,000×被保険者期間の月数×125/100+配偶者加給年金額
2級
平均標準報酬額(再評価)×5.481/1,000×被保険者期間の月数+配偶者加給年金額
3級
平均標準報酬額(再評価)×5.481/1,000×被保険者期間の月数
(最低保障額 584,500円)
- 平均標準報酬月額・平均標準報酬額は平成30年度の再評価率による。
- 1級と2級は、障害厚生年金と同時に障害基礎年金(子の加算を含む)が支給されます。
- 3級は報酬比例の年金のみの支給のため、加入期間が短いなどの理由で金額が低く なり過ぎないよう最低保証額があります。
②平成30年度は本来水準の額と従前額保障の額のうち高い方を支給しますので、それぞれ
式は2つになります。以降は、煩雑さを防ぐため、本来水準の額のみ提示します。
■報酬比例部分の従前額保障
○平成15年4月1日前の被保険者期間についての年金額
平均標準報酬月額(再評価)×10~7.5/1,000(生年月日に応じた率)×被保険者期間の月数
○平成15年4月1日前の被保険者期間についての年金額
平均標準報酬額(再評価)×7.692~5.769/1,000(生年月日に応じた率)×被保険者期間の月数
・平均標準報酬月額・平均標準報酬額は平成6年度の再評価率による。
・従前額改定率は、昭和13年4月2日以後生まれの人の場合、0.997。
昭和13年4月1日以前生まれの人の場合、0.999。
③被保険者期間の月数は、300月(25年)に満たない場合は300月で計算します。
加入期間が短い人の年金額が極端に少なくなってしますのを防止するためです。
④同一事由により国民年金法の障害基礎年金を受けることができない場合には、最低保証額(584,500円)が設けられています。一つは、上記のように3級の障害状態の人、一つは、65歳から70歳までの間に障害者になった場合です。厚生年金保険は勤めていれば70歳まで加入しますが、国民年金の第2号被保険者は、65歳時点で10年要件を満たしていればそこで終了です。したがって、65歳から70歳の間に障害者になると、1級または2級の障害状態に該当したとしても、障害厚生年金だけが支給されるという現象が起きるのです。
⑤被保険者期間の算定期間については、障害認定日の属する月後の被保険者期間は含めません。障害認定日の属する月分まで含めるということです。
配偶者加給年金額
障害等級1級または2級の場合は、配偶者加給年金額が加算されることがあります。
配偶者加給年金額:224,300円(平成30年度)
障害基礎年金は「子の加算」、障害厚生年金は「配偶者の加算」が対象となります。
障害等級1級または2級の障害厚生年金の受給権者が、その権利を取得した当時、
その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者があるとき、または、
受給権者がその権利を取得した後に生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を
有するに至ったときは、障害厚生年金の額に加給年金額が加算されます。
※生計維持は、将来にわたって年額850万円以上の収入を得られないと認められること
配偶者が65歳になった時は、加給年金額の支給は打ち切られ、配偶者の老齢基礎年金へ
振替加算されます。
障害手当金
3級よりも、もう少し軽い程度の障害が残ると、障害手当金が支給されます。障害手当金は一時金です。
傷病が治癒したものであって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。
支給要件
①初診日から5年を経過する日までの間に傷病が治っていること
②障害の状態が政令で定める状態にあること
③原則的な障害厚生年金と同様の保険料納付要件を満たしていること
額
障害等級2級の障害厚生年金の額の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額であり、一時金の額は、
平成15年4月1日前の被保険者期間と平成15年4月1日以後の被保険者期間を合算した額です。
平成15年4月1日前の被保険者期間についての障害手当金の額
平均標準報酬月額(再評価)×7.125/1,000×被保険者期間の月数×2+配偶者加給年金額
平成15年4月1日以後の被保険者期間についての障害手当金の額
平均標準報酬額(再評価)×5.481/1,000×被保険者期間の月数×2+配偶者加給年金額
・平均標準報酬月額・平均標準報酬額は平成30年度の再評価率による。
・生年月日に応じた乗率の読み替えは行わない(本来水準)
・被保険者期間の月数が300月に満たないときは300月とする
・最低保証額:584,500円(平成30年度)がある。
・障害厚生年金同様、従前額保障があり、本来水準の額と従前額保障の額のうち高い方を支給する。
・配偶者加給年金額は加算されません。
障害手当金(厚生年金保険法施行令)
・両眼の視力が0.6以下に減じたもの
・1眼の視力が0.1以下に減じたもの
・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
・両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
・両眼の調節機能及び輻輳(ふくそう)機能に著しい障害を残すもの
・1耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
・そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
・鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
・脊柱の機能に障害を残すもの
・1上肢の3大関節のうち、2関節に著しい機能障害を残すもの
・1下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
・1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
・長管状骨(上腕、前腕、大腿、下腿の管状の骨)に著しい転移変形を残すもの
・1上肢の2指以上を失ったもの
・1上肢のひとさし指を失ったもの
・1上肢の3指以上の用を廃したもの
・ひとさし指を併せ1上肢の2指の用を廃したもの
・1上肢のおや指の用を廃したもの
・1下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの
・1下肢の5趾の用を廃したもの
・前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
・精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
支給調整
障害の程度を定める日に、次のいずれかに該当する場合は支給されません。
①厚生年金法の年金たる保険給付の受給権者
②国民年金法による年金たる給付の受給権者
③同一の傷病について、国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法、公立学校の
学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する法律もしくは労働基準法の障害補償、労働者災害補償保険法の障害補償給付または船員保険法の障害給付を受ける権利を有する者
支給停止
障害基礎年金と同じです。
失権
障害基礎年金と同じです。
それでは、また次回をお楽しみに!!