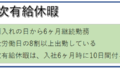労働基準法
パートタイム労働者などで、所定労働日数が少なくても所定労働日数に応じて年次有給休暇が比例付与される規定と、日単位による取得のほかに、時間単位による取得についての規定を解説していきます。
年次有給休暇(法39条の1 3項、4項)
第39条の1 Ⅲ 次に掲げる労働者(1週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間(30時間)以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第1号において「通常の労働者の週所定労働日数」(5.2日)という。)と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。
Ⅳ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)により、次に掲げる事項を定めた場合において、第1号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前3項の規定による有給休暇の日数のうちⅱに掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。
労働基準法施行規則 第24条の4 法第39条第4項第3号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
|
比例付与の対象者
パートタイム労働者等に対しても、6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合には、年次有給休暇を付与しなければならないが、これらの者のうち、通常の労働者と比して週所定労働日数等が相当程度少ない者については、その所定労働日数に比例した日数の年次有給休暇を付与(比例付与)することとされています。
比例付与の対象となる労働者は、基準日(雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務した日等の翌日)において、次のいずれかに該当する者である。
(1)1週間の所定労働時間が30時間未満で、かつ、1週間の所定労働日数が4日以下の労働者
(2)週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合には、1週間の所定労働時間が30時間未満で、かつ、1年間の所定労働日数が216日以下の労働者
比例付与の日数
比例付与の対象となる労働者については、その所定労働日数に応じ次の日数の年次有給休暇を付与することになる。
所定労働日数 | 継続勤務年数に応じた付与日数 | |||||||
週 | 1年間 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年 |
4日 | 169日~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
通常の労働者 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 | |
付与日数の計算方法は次の通りです。
【例】週4日勤務の場合
入社して6箇月後に付与される日数は、
10×(4/5.2)=7日(1日未満切捨て)となる。
入社して1年6箇月後に付与される日数は、
11×(4/5.2)=8日(1日未満切捨て)となる。
時間単位年休
労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るとともに、ゆとりある生活の実現にも資するという趣旨から、毎年一定日数の有給休暇を与えることを規定している。この年次有給休暇については、取得率が5割を下回る水準で推移しており、その取得の促進が課題となっている一方、現行の日単位による取得のほかに、時間単位による取得の希望もみられるところである。
このため、まとまった日数の休暇を取得するという年次有給休暇制度本来の趣旨を踏まえつつ、仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効に活用できるようにすることを目的として、労使協定により、年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を取得することができることとしています。(平成21.5.29基発0529001号)
労働者の意思による取得
時間単位年休に係る労使協定は、当該事業場において、労働者が時間単位による取得を請求した場合において、労働者が請求した時季に時間単位により年次有給休暇を与えることができることとするものであり、個々の労働者に対して時間単位による取得を義務付けるものではない。労使協定が締結されている事業場において、個々の労働者が時間単位により取得するか日単位により取得するかは、労働者の意思によるものである。(平成21.5.29基発0529001号)
1日単位の年次有給休暇を取得する場合の取扱い
時間単位年休は、年次有給休暇を有効に活用できるようにすることを目的として、原則となる取得方法である日単位による取得の例外として認められるものであり、1日の年次有給休暇を取得する場合には、原則として時間単位ではなく日単位により取得するものである。(同上)
労使協定で定める事項
労使協定で定める事項は次の4つである。
・時間単位年休の対象労働者の範囲
・時間単位年休の日数
・時間単位年休の1日の時間数
・1時間以外の時間を単位とする場合の時間数
(1)時間単位年休の対象労働者の範囲(法第39条第4項第1号関係)
年次有給休暇の権利は、法定要件を充たした場合法律上当然に労働者に生ずる権利であるが、その取得に際しては、事業の正常な運営との調整が考慮されるものである。この点において、時間単位による取得は、例えば一斉に作業を行うことが必要とされる業務に従事する労働者等にはなじまないことが考えられる。このため、事業の正常な運営との調整を図る観点から、法第39条第4項第1号において、労使協定では、時間単位年休の対象労働者の範囲を定めることとされていること。
なお、年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは労働者の自由であることから、利用目的によって時間単位年休の対象労働者の範囲を定めることはできないものであること。(平成21.5.29基発0529001号)
(2)時間単位年休の日数(法第39条第4項第2号関係)
時間を単位として与えることができる年次有給休暇の日数については、まとまった日数の休暇を取得するという年次有給休暇制度本来の趣旨にかんがみ、法第39条第4項第2号において、5日以内とされており、労使協定では、この範囲内で定める必要があること。
「5日以内」とは、法第39条第1項から第3項までの規定により労働者に与えられる1年間の年次有給休暇の日数のうち5日以内をいうものであること。法第39条第3項の規定により五日に満たない日数の年次有給休暇が比例付与される労働者については、労使協定では、当該比例付与される日数の範囲内で定めることとなること。
当該年度に取得されなかった年次有給休暇の残日数・時間数は、次年度に繰り越されることとなるが、当該次年度の時間単位年休の日数は、前年度からの繰越分も含めて5日の範囲内となるものであること。
(3)時間単位年休1日の時間数(則第24条の4第1号関係)
1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかについては、当該労働者の所定労働時間数を基に定めることとなるが、所定労働時間数に1時間に満たない時間数がある労働者にとって不利益とならないようにする観点から、則第24条の4第1号において、1日の所定労働時間数を下回らないものとされており、労使協定では、これに沿って定める必要があること。具体的には、1時間に満たない時間数については、時間単位に切り上げる必要があること。
「1日の所定労働時間数」については、日によって所定労働時間数が異なる場合には1年間における1日平均所定労働時間数となり、1年間における総所定労働時間数が決まっていない場合には所定労働時間数が決まっている期間における1日平均所定労働時間数となるものであること。
労使協定では、当該労働者の時間単位年休1日の時間数が特定されるように定める必要があるが、これが特定される限りにおいて、労働者の所定労働時間数ごとにグループ化して定めること(例えば、所定労働時間6時間以下の者は6時間、同6時間超7時間以下の者は7時間、同7時間超の者は8時間
等)も差し支えない。
等)も差し支えない。
【例】
1日の所定労働時間が7時間30分で5日分の時間単位年休がある場合
7時間30分を切り上げて1日8時間とする。
8時間×5日=40時間分の時間単位年休
(7時間30分×5日=37時間30分を切り上げて38時間ではない)
(4)1時間以外の時間を単位とする場合の時間数(則第24条の4第2号関係)
たとえば、2時間や3時間といったように、1時間以外の時間を単位として時間単位年休を与えることとする場合には、1日の所定労働時間数に満たない範囲内で、労使協定で、その時間数を定めなければならない。
「1日の所定労働時間数に満たないものとする」と定めているのは、1日の所定労働時間数と同じ又はこれを上回る時間数を時間単位年休の単位とすることは、時間単位年休の取得を事実上不可能にするものであることからである。
#労働基準法 #年次有給休暇 #比例付与 #時間単位年休

資格校紹介
2020年8月23日(日)に第52回社会保険労務士試験が実施されました。 今年度の受験申込者数は約49,200人でした。 合格率は10%を切るほどの難関資格の一つです。 しかし、働き方改革の影響もあり、社労士への期待とニーズは高まっているため多くの方が目指されています。あらゆることに共通しますが、何かを成し遂げようとするときには計画を立て目標に向けて実行し続けることが重要です。多くのライバルが存在するからこそ、学習を早めに始めることがとても大切になります。社労士資格校を紹介します。通学ではなく手軽にスキマ時間で学習できる資格校を選んでおります。

社労士試験用教材のご紹介
独学で取得を目指す方も多いですよね。私もその一人でした。しかし、勉強を始めるにあたりどのテキストを選べば良いのか、迷っている方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、そんな社労士試験用テキストをご紹介していきます。最短期間での合格を目指して、しっかり対策を立てていきましょう!

労働法関連書籍のおすすめ本(入門書~実務書)
労働法を入門から実務まで精通するための良本を紹介します。