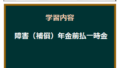障害(補償)給付
業務または通勤が原因となった負傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合には、障害補償給付(業務災害の場合)または障害給付(通勤災害の場合)が支給されます。
種類及び支給額 (法15条、法別表第1、第2)
Ⅰ 障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。
Ⅱ 障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、次表に規定する額とする。)
| 保険給付 | 障害等級 | 額 |
| 障害補償年金 | 第1級 第2級 第3級 第4級 第5級 第6級 第7級 | 1年につき給付基礎日額の313日分 1年につき給付基礎日額の277日分 1年につき給付基礎日額の245日分 1年につき給付基礎日額の213日分 1年につき給付基礎日額の184日分 1年につき給付基礎日額の156日分 1年につき給付基礎日額の131日分 |
| 障害補償一時金 | 第8級 第9級 第10級 第11級 第12級 第13級 第14級 | 給付基礎日額の503日分 給付基礎日額の391日分 給付基礎日額の302日分 給付基礎日額の223日分 給付基礎日額の156日分 給付基礎日額の101日分 給付基礎日額の56日分 |
【障害給付(法22条の3)】
Ⅰ 障害給付は、労働者が通勤により負傷し、又は疾病にかかり、なおったとき身体に障害が存する場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。
Ⅱ 障害給付は、第15条第1項の厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害年金又は障害一時金とする。
Ⅲ 第15条第2項[障害補償給付の額]、別表第1及び別表第2の規定は、障害給付について準用する。
■障害(補償)給付の種類

障害等級 (則14条1項、4項)
Ⅰ 障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、別表第1に定めるところによる。
Ⅱ 別表第1に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、同表に掲げる身体障害に準じてその障害等級を定める。
【障害給付(則18条の8,1項)】
第14条の規定は、障害給付について準用する。
・障害等級の準用
障害等級は、則別表第1の障害等級表に労働者の身体障害をあてはめて決定する。また、味覚や臭覚を脱失した場合などの障害等級表に定められていない身体障害の場合は、同表の身体障害に準じて定められる。
併合 (則14条2項、3項)
Ⅰ 別表第1に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。
Ⅱ 次のⅰからⅲに掲げる場合には、障害等級をそれぞれ当該ⅰからⅲに掲げる等級だけ繰り上げた障害等級による。ただし、本文の規定による障害等級が第8級以下である場合において、各の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額の合算額が本文の規定による障害等級に応ずる障害補償給付の額に満たないときは、その者に支給する障害補償給付は、当該合算額による。
ⅰ 第13級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 1級
ⅱ 第8級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 2級
ⅲ 第5級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 3級
【障害給付(則18条の8,1項)】
第14条の規定は、障害給付について準用する。
併合
同一の事故による身体障害が2以上あるときは、原則として、そのうち重い方をその身体障害の等級とする(併合)。例えば、第12級と第14級の場合は、第12級とする。しかし、この併合が適用されるのは、第14級の身体障害がある場合に限定される。
併合繰上げ
同一の事故による第13級以上の身体障害が2以上あるときは、以下のように併合繰上げを行う。
⑴ 第13級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を1級繰り上げる。
【例 】第12級と第13級の場合は、第11級とする。
なお、この方法によると第9級と第13級の場合は、第8級となるが、併合繰上げ後の障害等級による額(第8級で503日分)が、各障害等級に応ずる障害(補償)給付の額の合算額(第9級の391日分と第13級の101日分を加算して492日分)を上回るので、加算した額である492日分の一時金が支給される(この併合繰上げの特例が適用されるのはこのケースのみである。)。
⑵ 第8級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を2級繰り上げる。
【例 】第8級と第7級の場合は、第5級とする。
⑶ 第5級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を3級繰り上げる。
【例 】第5級と第4級の場合は、第1級とする。
【判例】
(業務災害による機能障害から派生した神経症状)
原審の確定した事実関係のもとにおいて、上告人の身体障害について労働者災害補償保険法施行規則別表第1所定の障害等級を認定するにつき、上告人の右膝関節部における機能障害とこれより派生した神経症状とを包括して一個の身体障害と評価し、その等級は前者(重い方)の障害等級によるべく同規則14条3項の規定により等級を繰り上げるべきものではないとした原審の判断は、正当として是認することができる。 (最一小昭和55.3.27障害等級決定取消請求事件)
加重 (則14条5項)
既に身体障害のあった者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害補償給付は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付とし、その額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額から、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額(現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償年金であって、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、その障害補償一時金の額を25で除して得た額)を差し引いた額による。
【障害給付(則18条の8,1項)】
第14条の規定は、障害給付について準用する。
「加重」とは
業務災害又は通勤災害によって新たに障害が加わった結果、障害等級表上、現存する障害が既存の障害より重くなった場合をいうので、自然的経過又は既存の障害の原因となった疾病の再発により障害の程度を重くした場合は「加重」に該当しない。
「同一の部位」とは
完全に同一の場所ということではなく、例えば、右眼と左眼の場合も含まれる。
給付額
⑴ 加重の前後ともに年金相当の場合
加重後の障害等級に応ずる障害(補償)年金の額 - 加重前の障害等級に応ずる障害(補償)年金の額
⑵ 加重の前後ともに一時金相当の場合
加重後の障害等級に応ずる障害(補償)一時金の額 - 加重前の障害等級に応ずる
障害(補償)一時金の額
⑶ 加重前が一時金相当で加重後が年金相当の場合
加重後の障害等級に応ずる障害(補償)年金の額 - 加重前の障害等級に応ずる障害(補償)一時金の額 × 1/25
・既存の障害は業務上又は通勤によるものであるか否かは問わない。
・既存の障害で既に障害(補償)年金を受けている労働者は、加重の結果、新たに差額支給相当額の障害(補償)年金の受給権を取得することになる(同一労働者が同時に2以上の障害(補償)年金の受給権を取得することがある。)。
変更 (法15条の2)
障害補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金を支給するものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しない。
【障害給付(法22条の3,3項)】
第15条の2[障害補償年金の変更]の規定は、障害給付について準用する。
・変更とは
変更の扱いは、障害(補償)年金の支給事由となっている障害の程度が新たな傷病によらず、又は傷病の再発によらず、自然的に変更した場合に行われます。
(具体的な取扱い)
⑴ その変更が、障害等級第1級から第7級の範囲内であるときは、その変更のあった月の翌月の分から新たに該当するに至った障害等級に応ずる年金額に改定する。
⑵ その変更が、障害等級第8級以下(第14級以上)に及ぶときは、障害(補償)年金の受給権が消滅するので、その月分をもって障害(補償)年金の支給を打ち切り、障害(補償)一時金を支給する。 (昭和41.1.31基発73号)
再発 (昭和41.1.31基発73号)
Ⅰ 障害(補償)年金の受給権者の負傷又は疾病が再発した場合は、次のようになる。
ⅰ 従前の障害(補償)年金の支給は、その月分をもって打ち切られる。
ⅱ 再発による療養の期間中は、療養(補償)給付等が支給される。
ⅲ 再治ゆ後残った障害については、治ゆ後の新たな障害等級に応ずる年金又は一時金が支給される。
Ⅱ 障害(補償)一時金の支給を受けた者の負傷又は疾病が再発した場合は、次のようになる。
ⅰ 再治ゆ後に残った障害の程度が従前の障害より軽減したときは、再治ゆ後に残った障害については、給付は行われない。
ⅱ 再治ゆ後残った同一部位の障害の程度が以前の障害の程度より悪化したときは、「加重」の取扱いに準じ、差額支給が行われる。



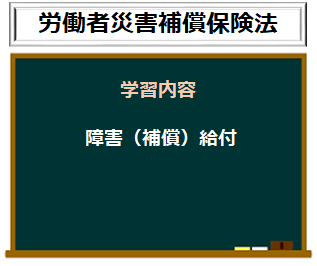
年金/障害の程度の変更-120x68.png)