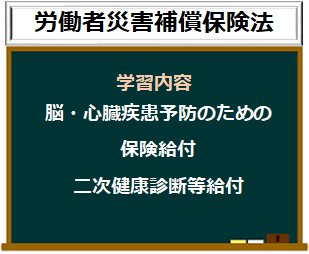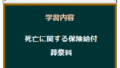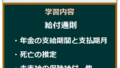脳・心臓疾患予防のための保険給付
二次健康診断等給付
労働安全衛生法に基づいて行われる定期健康診断等のうち、直近のもの(「一次健康診断」といいます)において、脳・心臓疾患に関連する一定の項目に異常の所見がある場合に、二次健康診断等給付が受けられます。
支給要件 (法26条1項)
二次健康診断等給付は、労働安全衛生法第66条第1項[一般健康診断]の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第5項ただし書[労働者指定医師による健康診断]の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。
趣旨
「過労死」等の原因である脳血管・心臓疾患の発生を予防するため、労働安全衛生法に規定する定期健康診断等の一次健康診断において、一定の項目について異常所見があると診断された労働者については、二次健康診断及びその結果に基づく保健指導が行われます。
一次健康診断
労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断とは、雇入れ時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断及び給食従業員の検便であるが、給食従業員の検便については、血圧検査、血液検査等の業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査が行われないことから、一次健康診断の対象とはならない。
二次健康診断等給付の対象者
一次健康診断の結果、次のすべての検査項目について、「異常の所見」があると診断された労働者が二次健康診断等給付の対象者となります。
- 血圧の測定
- 血中脂質検査〔低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)又は血清トリグリセライドの量の検査〕
- 血糖検査
- 腹囲の検査又はBMI〔体重(kg)/身長(m)2〕の測定 (則18条の16)
なお、一次健康診断の担当医師により、①から④の検査項目において「異常なし」と診断された場合であっても、労働安全衛生法に基づき事業場に選任されている産業医等が、就業環境等を総合的に勘案し、異常の所見を認めた場合には、産業医等の意見を優先します。
- 二次健康診断等給付は、労災保険の特別加入者には支給されない。
特別加入者の健康診断の受診は自主性に任されていることから、特別加入者は二次健康診断給付の対象者とはなりません。(平成13.3.30基発233号)
- 一次健康診断の結果その他の機会で、医師により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる者については二次健康診断等給付の対象とはならない(既にこれらの疾患の症状を有すると認められる者については、予防ではなく治療の対象になるため)。
給付の範囲 (法26条2項、3項)
二次健康診断等給付では、二次健康診断と特定保健指導があります。
Ⅰ 二次健康診断等給付の範囲は、次のとおりとする。
ⅰ 脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査(第26条第1項に規定する検査を除く。)であって厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(1年度につき1回に限る。以下「二次健康診断」という。)
ⅱ 二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導(二次健康診断ごとに1回に限る。以下「特定保健指導」という。)
Ⅱ 政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないものとする。
二次健康診断 - 二次健康診断(1年度につき1回に限る)
- 特定保健指導(二次健康診断ごとに1回に限る)
二次健康診断の検査項目
二次健康診断は、脳血管と心臓の状態を把握するために必要な検査で、具体的には、次の検査を行います。
①空腹時血中脂質検査
空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)および血清トリグリセライド(中性脂肪)の量により血中脂質を測定する検査
②空腹時血糖値検査
空腹時において血液を採取し、食事により影響を排除した血中グルコースの量(血糖値)を測定する検査
③ヘモグロビンA1c(エーワンシー)検査
食事による一時的な影響が少なく、過去1~2か月間における平均的な血糖値を表すとされているヘモグロビンA1cの割合を測定する検査
④負荷心電図検査または胸部超音波検査(心エコー検査)のいずれか一方の検査
・負荷心電図検査
階段を上り下りするなどの運動により心臓に負荷を加えた状態で、心電図を計測する検査胸部超音波検査
・超音波探触子を胸壁に当て、心臓の状態を調べる検査
⑤頸部超音波検査(頸部エコー検査)
超音波探触子を頸部に当て、脳に入る動脈の状態を調べる検査
⑥微量アルブミン尿検査
尿中のアルブミン(血清中に含まれるタンパク質の一種)の量を精密に測定する検査
※一次健康診断の尿蛋白検査で、擬陽性(±)または弱陽性(+)の所見が認められた場合に限ります。
支給回数
二次健康診断は、1年度につき1回に限り、特定保健指導は、二次健康診断ごとに1回に限る。したがって、同一年度内に1人の労働者に対して2回以上の定期健康診断等を実施している事業場であっても、一次健康診断において給付対象所見が認められる場合に当該年度内に1回に限り支給する。 (平成13.3.30基発233号)
なお、一次健康診断を実施した次の年度に当該一次健康診断に係る二次健康診断等給付を支給することは可能である。ただしその場合は、当該年度に実施した定期健康診断等について、同一年度内に再度二次健康診断等給付を支給することはできない。 (平成13.3.30基発233号)
特定保健指導
特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき、脳・心臓疾患の発症の予防を図るため、医師または保健師の面接により行われる保健指導です。特定保健指導は、次の指導の全てを行うものとされています。
①栄養指導
適切なカロリーの摂取等、食生活上の指針を示す指導
②運動指導
必要な運動の指針を示す指導
③生活指導
飲酒、喫煙、睡眠等の生活習慣に関する指導
(平成13.3.30基発233号)
なお、二次健康診断の結果、脳・心臓疾患の症状を有していると診断された場合は特定保健指導は、行なわれません。
医師の意見聴取
二次健康診断を受けた労働者から当該二次健康診断の実施の日から3箇月以内に当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該二次健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を、当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2月以内に、聴かなければならない。 (法27条、則18条の17、則18条の18、安衛法66条の4、安衛則51条の2,2項1号)
事後措置
事業主は、二次健康診断の結果についての医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。(安衛法66条の5、平成13.3.30基発233号)
なお、二次健康診断の場合も、聴取した医師の意見は、健康診断個人票に記載しなければならない。 (法27条、則18条の18、安衛法66条の4、安衛則51条の2,2項2号)
受給手続 (則11条の3,1項、則18条の19,1項、4項)
Ⅰ 二次健康診断等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所(以下「健診給付病院等」という。)において行う。
Ⅱ 二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
Ⅲ 二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断を受けた日から3箇月以内に行わなければならない。ただし、天災その他請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。