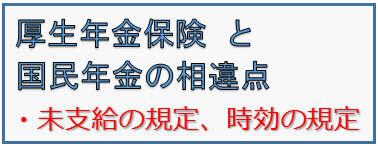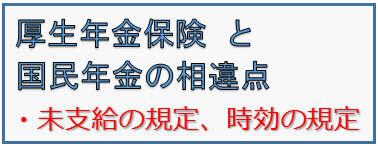未支給の規定および時効について国民年金との違い
裁定、端数処理、年金の支給期間および支払期月、死亡の推定および失踪宣告の場合の取扱い、年金の支払いの調整、損害賠償請求権、受給権の保護および公課の禁止、時効等の規定は、すべて国民年金と同様ですので、割愛させていただきます。ただし、以下の点にご注意ください。
未支給の規定
国民年金は「未支給年金」、厚生年金保険は「未支給の保険給付」です。未支給の対象となる(保険)給付は、国民年金では年金のみですが、厚生年金保険では一時金も含まれるということです。
ご参考
未支給年金とは
未支給年金は、亡くなった方が年金を受け取らないまま亡くなってしまった場合の、未支給分の年金のことを指します。未支給年金は、年金を受け取る前に亡くなったか、あるいは年金を請求しないうちに亡くなってしまった場合に、遺族が請求できます。
未支給年金を受け取れる人
(優先順位) (遺族)
1 … 配偶者
2 … 子
3 … 父母
4 … 孫
5 … 祖父母
6 … 兄弟姉妹
7 … 上記以外の3親等内の親族
※年金は、2ケ月に1度、偶数月の15日に振り込まれます。年金は、死亡した月分まで支給されると定められているため、7月1日に死亡した場合は、6・7月分を8月15日に2ケ月分を、8月1日に死亡した場合は、8月分を10月15日に1ケ月分を受け取ることができます。年金は、通常後払いの形で支払われるため、年金を受給していた場合は必ず未支給年金が発生します。遺族が未支給年金を受け取る場合は、遺族が請求手続きを行う必要があります。
時効
国民年金の死亡一時金は2年ですが、厚生年金では、以下の通り一時金も5年です。
・保険給付その徴収金の徴収または還付を受ける権利 …2年
・保険給付(年金および一時金)を受ける権利 …5年
上記の説明項目が少ないので過去問をやってみましょう!
(H24問6)
厚生年金保険法における滞納処分等については、国税滞納処分の例によって行うこととされており、日本年金機構が滞納処分等を行う場合には、あらかじめ財務大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規定に従い、徴収職員に行わせなければならない。
⇒誤り 「財務大臣」ではなく「厚生労働大臣」の認可を受けなければなりません。
(H25問4)
厚生労働大臣は、督促を受けた納付義務者が指定の期限までに保険料等を納付しないとき、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所有地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法に規定される指定都市にあっては区とする。)に対して、その処分を請求することができる。
⇒正しい。滞納処分を請求された市町村は市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合、厚生労働大臣は、その手数料として、徴収金の100分の4に相当する額を市町村に交付しなければならない。
(H12問1)
保険料の還付を受ける権利の消滅時効は2年であり、保険給付を受ける権利の消滅時効は5年である。
⇒正しい。年金および一時金を受ける権利は、厚生年金保険では5年である。
(H18問3)
老齢厚生年金の受給権者が裁定請求をしないまま死亡した場合において、死亡するまでに受けるべきであった給付の申請を行う者は、死亡した受給権者と生計を同じくしていたことを証する書類及びその他の書類を、その者の死亡時から5年以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
⇒誤り。「その者の死亡時から」ではなく「その者が老齢厚生年金の受給権を取得した時から」です。