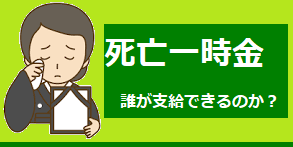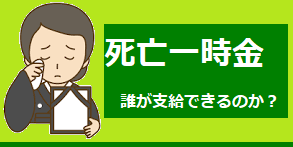今回は、死亡一時金について解説します。死亡一時金も寡婦年金と同様、国民年金独自の給付です。寡婦年金は妻だけに支給されるものでしたが、死亡一時金は一定の遺族に支給されるものです。死亡一時金も、遺族基礎年金を受けることのできる遺族がいない場合に支給される保険料の掛け捨て防止を目的とする給付なのですね。
死亡一時金
たとえば、子のない夫婦がいて、第1号被保険者である妻が亡くなったとします。子がいないので、夫は遺族基礎年金は受給できません。寡婦年金はというと、寡婦の「婦」は婦人の婦ですから、女性しか受給できません。結果、夫には何も支給されないこととなり、妻が長年支払った保険料が無駄になってしまいます。そこで掛け捨て防止のために死亡一時金を支給することとしたのです。
支給要件
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る次の①から④の月数を合算した月数が36月(3年)以上である者が死亡したこと
①保険料納付済期間の月数
②保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数
③保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数
④保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数
遺族の範囲
死亡した者の遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給されます。
補足
障害厚生年金等の配偶者加給年金は以前説明しましたが、その場合は「生計維持」が
要件でした。「生計を同じくする」との違いは何でしょう?
「生計維持」とは、下記の2つの要件が必要です。
①生計を同じくしていること、、つまり生計同一であること
②収入が一定額以下であること
以上2つの条件をいずれも満たす人になります。
簡単に言えば、生活費の大半は夫(妻)の給与で賄われていること。
「生計を同じく」は生計を同じくするだけでよく、収入額については問われない、
ということになります。
試験では細かい違いをついてくることもありますので注意してください。
死亡一時金が支給されない場合
①死亡したものが、老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがある場合
②死亡したものの死亡日において、その者の死亡により遺族基礎年金を受けることが
できる者があるとき
(死亡日の属する月に遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く)
⇒父の死亡月に子が18歳の年度末に達したようなケースです。年金の支給は翌月
からですから、この子はいったん遺族基礎年金の受給権を得ていますが、結局
一度も支給を受けていません。そこで、死亡一時金を支給することとしたのです
③遺族基礎年金の受給要件を満たす胎児であった子が生まれたことにより、妻または胎児
であった子が遺族基礎年金の受給権を取得したとき
(胎児が生まれた日の属する月に、遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く)
⇒子が生まれてすぐに死亡したようなケースです。
遺族基礎年金を受けることができる場合は、死亡一時金は支給されません。
死亡一時金は、保険料の掛け捨て防止ですから、当然ですね。
支給額
合算した月数 | 支給額 |
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
※付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上ある場合は、一律に8,500円が加算されます。
寡婦年金との選択
死亡一時金の支給を受ける者が寡婦年金の支給を受けることができるときは、その者の選択により、どちらか一方が支給されます。
それでは、また次回をお楽しみに!!
https://taka-src.com/%e8%b3%87%e6%a0%bc%e6%a0%a1%e7%b4%b9%e4%bb%8b