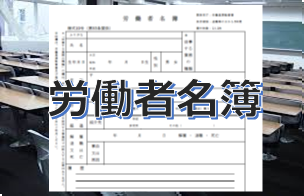労働基準法
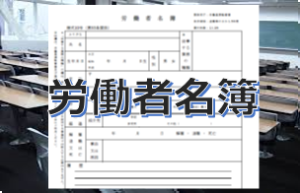
労働者名簿
労働者名簿とは、法定3帳簿のひとつで、従業員を雇う場合に作成、整備する義務がある書類です。労働者名簿は、労働者の氏名や採用した日など企業が雇用している従業員の情報を記した書類のことです。労働者名簿は、会社の規模などに関係なく、従業員を雇い入れている場合は、労働基準法第107条によって、作成、整備が義務づけられています。
労働者名簿は、従業員を雇う場合、そもそも法律によって作成が定められた書類であることに加え、会社の適切な労務管理の点からも重要な書類です。
ちなみに、法定3帳簿とは、労働基準法によって、会社の規模に関わらず、設置が義務づけられた、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿のことを指します。
労働者名簿(法107条)
(労働者名簿)第107条
Ⅰ 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
Ⅱ Ⅰの規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。
1.労働者名簿の設置義務がある企業
労働者名簿は、従業員を雇っている会社に作成、整備する義務があります。会社の規模によって異なる者ではありません。従業員を雇っていれば法人、個人にかかわらず作成、整備しなければなりません。個人事業主であっても、従業員を雇っている場合は、労働者名簿を作成、整備する必要があります。
2.労働者名簿の対象になるのは
労働者名簿を作成する必要がある従業員は、原則としてすべての従業員です。正社員やパートなど雇用形態に関係なく、雇用しているという時点で作成の義務があります。ただし、日雇労働者については一時的なものですので記載義務はありません。
3.各事業場ごとに
労働者名簿は、事業場ごとに調製することを要する。したがって、1企業に2以上の事業場がある場合は、それぞれ別個に労働者名簿を調整しなければならない。
4.労働者名簿記載事項
労働者名簿には、次の事項を記入しなければならない。
- 氏名
- 生年月日
- 履歴
異動や昇進など、社内での履歴のこと。 - 性別
- 住所
- 従事する業務の種類
- 雇入れの年月日
採用が決定した日ではなく、実際に雇用を開始した日。 - 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)
従業員の都合により退職があった場合は、特に理由を記載する必要はありません。しかし、会社側で従業員を解雇した場合は、なぜ解雇したのか事由を記載する必要があります。 - 死亡の年月日及びその原因
従業員が在職中に死亡した場合、労災にあたるかどうか労務においては重要なポイントとなります。死亡した場合は、合わせて死亡の原因を記載しなければなりません。
なお、常時30人未満の労働者を使用する事業においては、「⑥従事する業務の種類」は記入しなくてよい。(法107条第1項、則53条)
5.労働者名簿の更新について
労働者名簿は、社員の異動などがあった度に記載するべきなのか、期間を定めて定期的に記載するべきなのか判断に迷うことがあるかもしれません。しかしながら、更新については、労働基準法施行規則第53条で遅延なくとされています。つまり、変更があれば、変更の度に更新しなければならないので注意しましょう。
※「遅滞なく」・・・「直ちに・速やかに・遅滞なく」は、どれも「すぐに」という意味の法律用語ですが、どのくらいすぐなのか、早さで違ってきます。最も時間的即時性が強く求められるのが「直ちに」、その次が「速やかに」、この3つの中では最も即時性の弱いのが「遅滞なく」であるとされています。
6.保存期間と起算日
労働者名簿を含む法定3帳簿は、3年の保存期間が定められています。労働者名簿の場合、従業員の退職や解雇、または死亡日から起算して3年となります。在職中の従業員の名簿と混同しないためにも、退職や解雇などがあった場合は、別ファイルなどとしてまとめておくと良いでしょう。
通達
(派遣労働者の労働者名簿と賃金台帳)
「労働者名簿」、「賃金台帳」及び「派遣元管理台帳」については、法令上記載しなければならない事項が具備されていれば、合わせて1つの台帳を作成してもよい。(昭和61.6.6基発333号)
・日日雇入れられる者については、労働者名簿を調整しなくてよい。
・派遣労働者の場合、労働者名簿や賃金台帳は、派遣元の使用者が調整しなければならない。(労働者派遣法44条)