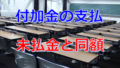労働基準法
時効
労働基準法で定められている賃金、災害補償、有給休暇などの請求権の時効は2年です。ただし、退職金の請求権だけは例外的に5年です。
時効(法115条)
(時効)第115条
労働基準法の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、労働基準法の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
法第115条の適用を受ける請求権【消滅時効にかかる年数】
1.賃金請求権【2年】
労基法11条によれば,賃金とは、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」とされています。
この「賃金」には、月給、週給、日給など定期的に支払われる賃金はもとより、通貨以外のもので支払われるもの、時間外・休日労働に対する割増賃金、年次有給休暇期間中の賃金等も含まれます。
2.退職手当請求権【5年】
労基法第115条のいう「退職金」は、就業規則、労働協約、労働契約等によって、それを支給すること及び支給基準が明確に定められているものをいいます。
この退職金は労働の対価として賃金に該当し、当然に会社が支払い義務を負うものです。
3.その他の請求権【2年】
◆災害補償請求権
◆金銭給付請求権
◆解雇予告手当請求権
◆年次有給休暇
◆退職時証明、物品の返還
◆帰郷旅費請求権 など
時効の起算点と中断
時効の起算点は一般的に、「具体的に権利が発生したとき」つまり各「賃金の支払い日」となります。
しかし、この時効の進行中に「請求」等の一定の事実が生じた時には、それまで経過した時効期間がリセットされる「時効の中断」となります。
中断事由は、労働基準法には定めがありませんが、民法により、①請求、②差押、③承認④催告などが定められています。
①②③いずれかの事実があれば時効は中断し、中断事由が終了したときから、改めて新たに時効期間が進行するということです。
④の催告とは、裁判外での請求のことを言いますが、請求したことを証明するためには、内容証明による文書で通知する必要があります。
内容証明によって催告した場合には、時効の完成を6ヶ月遅らせることが出来ます。 あくまで「暫定的時効中断」であり、この6ヶ月が経過する前に裁判上の請求をしないと、遡って時効が完成となります。
(退職時の証明の時効)
退職時の証明についての請求権の時効も退職時から2年である。(平成11.3.31基発169号)
解雇予告手当は、解雇の意思表示に際して支払わなければ解雇の効力を生じないものと解されるので、一般には解雇予告手当については時効の問題は生じない。(昭和27.5.17基収1906号)
皆さんご存知だと思いますが、年次有給休暇は、付与された日から2年間は取得できる権利があります。年次有給休暇が与えられて2年以内に取得しなかった場合は、取得できる権利が消滅します。その理由はこの時効の規定が根拠です。
https://taka-src.com/%e8%b3%87%e6%a0%bc%e6%a0%a1%e7%b4%b9%e4%bb%8b