労働基準法
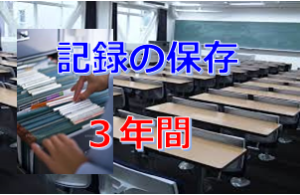
記録の保存
会社と従業員の間で紛争が生じたり、労働基準監督署が調査をしたりするときに、その証拠を残しておくために保存期間が決められています。
記録の保存(法109条)
(記録の保存)第109条
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
1.その他労働関係に関する重要な書類
その他労働関係に関する重要な書類とは、例えば、出勤簿、タイムカード、36協定書、残業命令書及びその報告書などである。(平成29.1.20基発0120第3号)
2.保存すべき期間の起算日
保存すべき期間の起算日は次の通りである。
| 書類の種類 | 保存すべき期間の起算日 |
| 労働者名簿 | 労働者の死亡、退職又は解雇の日 |
| 賃金台帳 | 最後の記入をした日 |
| 雇入れ又は退職に関する書類 | 労働者の退職又は死亡の日 |
| 災害補償に関する書類 | 災害補償を終った日 |
| 賃金その他労働関係に関する重要な書類 | その完結の日 |
(則56条)
ご参考
労働基準法以外にも関連する法律ごとに、書類の保存期間が定められています。具体的には、次のとおりです。
| 保存期間 | 書類名 | 法律 |
| 5年 | 健康診断の結果 | 労働安全衛生法 |
| 4年 | 雇用保険の従業員に関する書類 | 雇用保険法 |
| 3年 | 労災保険に関する書類 | 労災保険法 |
| 2年 | 健康保険に関する書類 | 健康保険法 |
| 2年 | 厚生年金保険に関する書類 | 厚生年金保険法 |
| 2年 | 雇用保険に関する書類 | 雇用保険法 |

資格校紹介
2020年8月23日(日)に第52回社会保険労務士試験が実施されました。 今年度の受験申込者数は約49,200人でした。 合格率は10%を切るほどの難関資格の一つです。 しかし、働き方改革の影響もあり、社労士への期待とニーズは高まっているため多くの方が目指されています。あらゆることに共通しますが、何かを成し遂げようとするときには計画を立て目標に向けて実行し続けることが重要です。多くのライバルが存在するからこそ、学習を早めに始めることがとても大切になります。社労士資格校を紹介します。通学ではなく手軽にスキマ時間で学習できる資格校を選んでおります。

社労士試験用教材のご紹介
独学で取得を目指す方も多いですよね。私もその一人でした。しかし、勉強を始めるにあたりどのテキストを選べば良いのか、迷っている方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、そんな社労士試験用テキストをご紹介していきます。最短期間での合格を目指して、しっかり対策を立てていきましょう!

労働法関連書籍のおすすめ本(入門書~実務書)
労働法を入門から実務まで精通するための良本を紹介します。



