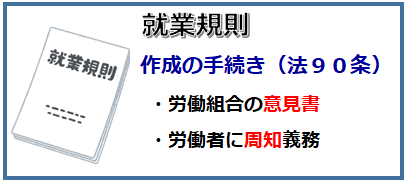
労働基準法
就業規則を作成、届出をする際には、労働組合(労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者)からの意見書を添付しなければなりません。
なお、労働者の過半数が仮にこの就業規則に反対であったとしても、協議があったことが客観的に認められる場合は届出は受理され、就業規則の効力に影響はありません。また、労働者に周知する義務があります。
就業規則作成の手続(法90条)
第90条
Ⅰ 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
Ⅱ 使用者は、前条[就業規則の作成及び届出]の規定により届出をなすについて、Ⅰの意見を記した書面を添付しなければならない。
労働基準法施行規則 第49条
Ⅱ 法第90条第2項の規定により前項[就業規則の届出]の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の署名又は記名押印のあるものでなければならない。
(法令等の周知義務)
第106条 使用者は、この労働基準法及び労働基準法に基づく命令の要旨、就業規則、労働基準法に基づく労使協定並びに労使委員会の決議を常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。
就業規則の作成手続の流れ
<作成義務あり>常時10人以上の労働者を使用する事業場
↓
就業規則作成・変更
↓
労働者の過半数で組織する労組等の意見を聴く
↓
意見書(署名or記名押印要)添付して届出
↓
所轄労働基準監督署長
↓
就業規則作成・変更
↓
労働者の過半数で組織する労組等の意見を聴く
↓
意見書(署名or記名押印要)添付して届出
↓
所轄労働基準監督署長
就業規則は、その作成及び届出義務が既定されているだけでなく、法第106条第1項の規定に基づき、労働者に周知させることも使用者に義務づけられている。
趣旨
労働基準法第90条第1項が、就業規則の作成又は変更について、当該事業場の過半数労働組合、それがない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことを使用者に義務づけた趣旨は、使用者が一方的作成・変更しうる就業規則に労働者の団体的意思を反映させ、就業規則を合理的なものにしようとすることにある。
一部の労働者に適用される別個の就業規則についての意見徴収
同一事業場において一部の労働者についてのみ適用される就業規則を別に作成することは差し支えないが、当該一部の労働者に適用される就業規則も当該事業場の就業規則の一部分であるから、その作成又は変更に際しての法第90条の意見の聴取については、当該事業場の全労働者の過半数で組織する労働組合又は全労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことが必要である。なお、これに加えて、その対象となる一部の労働者で組織する労働組合又は当該一部の労働者の過半数代表者の意見を聴くことが望ましい。
(昭和23.8.3基収2446号、昭和63.3.14基発150号)
派遣元の事業場における意見聴取
派遣元の使用者は、当該派遣元の事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。この場合の労働者とは、当該派遣元の事業場のすべての労働者であり、派遣中の労働者とそれ以外の労働者との両方を含むものである。
なお、派遣中の労働者が異なる派遣先に派遣されているため意見交換の機会が少ない場合があるが、その場合には代表者選任のための投票等に併せて就業規則案に対する意見を提出させ、これを代表者が集約する等により派遣労働者の意思が反映されることが望ましい。(昭和61.6.6基発333号)
参考通達
就業規則の受理
労働基準法第90条第2項は、就業規則の行政官庁への届出の際に、当該事業場の過半数労働組合、それがない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を記した書面を添付することを使用者に義務づけているが、過半数労働組合もしくは過半数代表者が故意に意見を表明しない場合又は意見書に署名もしくは記名押印をしない場合は、意見を聴いたことが客観的に証明できる限り、これを受理するよう取り扱うものとされている。
(昭和23.10.30基発1575号)
意見聴取の程度
「労働組合等の意見を聴かなければならない」とは、労働組合等との「協議決定」を要求するものではない。すなわち、労働組合等の意見の内容が当該就業規則に全面的に反対するものであっても、労働協約に協議決定又は同意を要する旨の記載がある等の特殊な場合を除き、就業規則の効力に影響がない。(昭和24.3.28基発373号、昭和25.3.15基収525号)
就業規則による労働契約の内容の変更
使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、労働契約法第10条[就業規則による労働契約の内容の変更-合意の原則の例外]の場合は、この限りでない。(労働契約法第9条)
就業規則による労働契約の内容の変更-合意の原則の例外
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、労働契約法第12条[就業規則違反の労働契約]に該当する場合を除き、この限りでない。(労働契約法10条)
<判例>
就業規則の不利益変更
新たな就業規則の作成又は変更によって、労働者の危篤の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として許さないと解すべきであるが、労働条件の集合的処理、特にその統一的かつ画一的な決定を建前とする就業規則の性質からいって、当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒むことは許されないと解すべきである。(最大判昭和43.12.25秋北バス事件)
就業規則の効力と周知
使用者が労働者を制裁として懲戒するためには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する。そして、就業規則が法的規範としての性質を有する者として、拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続きが取られていることを要する。(最三小昭和54.10.30国鉄札幌運転区事件、最大判昭和43.12.25秋北バス事件、最二小平成15.10.10フジ興産事件)
<Point> l 就業規則の作成又は変更の際には、労働組合等の意見を聴くのであって、同意を得る必要はない。 l 就業規則の一部変更の場合でも、所轄労働基準監督署長の命令により変更する場合でも、労働組合等の意見を聴かなければならない。 |

資格校紹介
2020年8月23日(日)に第52回社会保険労務士試験が実施されました。 今年度の受験申込者数は約49,200人でした。 合格率は10%を切るほどの難関資格の一つです。 しかし、働き方改革の影響もあり、社労士への期待とニーズは高まっているため多くの方が目指されています。あらゆることに共通しますが、何かを成し遂げようとするときには計画を立て目標に向けて実行し続けることが重要です。多くのライバルが存在するからこそ、学習を早めに始めることがとても大切になります。社労士資格校を紹介します。通学ではなく手軽にスキマ時間で学習できる資格校を選んでおります。

社労士試験用教材のご紹介
独学で取得を目指す方も多いですよね。私もその一人でした。しかし、勉強を始めるにあたりどのテキストを選べば良いのか、迷っている方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、そんな社労士試験用テキストをご紹介していきます。最短期間での合格を目指して、しっかり対策を立てていきましょう!

労働法関連書籍のおすすめ本(入門書~実務書)
労働法を入門から実務まで精通するための良本を紹介します。
リンク


