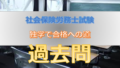労働基準法
両罰規定
労基法は、近代刑法の原則に基づき、行為者処罰の建前をとり、労基法10条でいう使用者の違反行為が処罰の対象となっています。もっとも、使用者概念は極めて広く、取締役・工場長等は言うまでもなく、支店長・課長・現場監督等々の下級職員も含み得ます。これらのいわゆる従業者たる使用者が、法違反を犯せば当然処罰されます。
しかしながら、違反行為をした者が事業主でない場合(従業員)の場合には、事業主のために事業主に対する義務の履行として法違反行為をなしているのが現実であり、その利益を享受する事業主が全く処罰されないのは妥当ではありません。
そこで、そのような場合には利益の帰属者である事業主にも責任を負わせることとし、労働基準法の違反防止を完全ならしめようとするものである。
両罰規定(法121条)
第121条
Ⅰ 労働基準法の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。Ⅱにおいて同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。
Ⅱ 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。
1.事業主
上記Ⅰ本文の「事業主」は、経営主体(個人企業の場合は個人企業主、法人組織の場合は法人そのもの)を指し、上記Ⅰただし書及びⅡの「事業主」は、その事業主を代表して違反行為の防止に必要な措置を講じる自然人(個人企業主、法人の代表者、法定代理人)を指す。
2.事業主も行為者として罰する
上記Ⅰは、事業主の注意義務を前提とした過失責任として事業主に対する処罰は罰金刑とされている。
上記Ⅱは、事業主自身が積極的に違反防止措置を講ぜず、是正措置をなさず、さらには教唆したような場合は、現実の行為者でなくても行為者として処罰しようとするもので罰金刑に限らない。
3.代理人、使用人その他の従業者
原則としては、労基法10条にいう事業主以外の使用者がほぼこれに該当することとなります。具体的には、支配人などが「代理人」の例であり、「代理人、使用人以外の従業員」としては、代表権なき取締役がその典型例といえます。(昭和23.3.17基発461号、昭和23.2.13基発90号)。
「その他の従業者」は従業員と考えてみてください。
通達
(事務代理の懈怠と罰則の適用について)
法令の規定により事業主等に申請等が義務づけられている場合において、事務代理の委任を受けた社会保険労務士がその懈怠により当該申請等を行わなかった場合には、当該社会保険労務士は、労働基準法第10条にいう「使用者」及び各法令の両罰規定にいう「代理人、使用人その他の従業者」に該当するものであるので、当該社会保険労務士を当該申請等の義務違反の行為者として各法令の罰則規定及び両罰規定に基づきその責任を問い得るものであること。
また、この場合、事業主等に対しては、事業主等が社会保険労務士に必要な情報を与える等申請等をし得る条件を整備していれば、通常は、必要な注意義務を尽くしているものとして免責されるものと考えられるが、そのように必要な注意義務を尽くしたものと認められない場合には、当該両罰規定に基づき事業主等の責任をも問い得るものであること。(昭和62.3.26基発169号)
(事業主が法人である場合)
事業主が法人である場合には、行為者たる社長を処罰するのか外事業主たる法人も労働基準法第121条第1項により罰金刑を科することができる。(昭和24.4.18検務10882号)