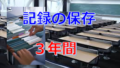労働基準法

賃金台帳
前回同様、労働基準法では、労働者を雇用する企業に対し、労働者名簿や賃金台帳、出勤簿等を整備し、保存することを義務づけています。これらは「法定3帳簿」とも呼ばれ、適切に整備していない場合は処罰の対象となります。また、労働者の適切な労務管理のためにも、法定3帳簿をきちんと整備しておくことが必要です。
労働基準法第108条は、企業に対し、各事業場ごとに「賃金台帳」を作成し、賃金計算の基礎となる事項や賃金の額などについて賃金の支払いのたびに遅滞なく記入することを義務づけています。
労働者名簿とは異なり、賃金台帳は日雇い労働者も含めたすべての労働者について作成しなければなりません。また、賃金台帳は賃金が支払われるたびに記入しなければならないことから、毎月1回必ず書き足されていくことになります。
賃金台帳(法108条)
各事業場ごとに
賃金台帳は、事業場ごとに調製することを要する。したがって、1企業に2以上の事業場がある場合は、それぞれ賃金台帳を別個に調整しなければならない。
賃金台帳記載事項
使用者は、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければなりません。
- 氏名
- 性別
- 賃金計算期間
- 労働日数
- 労働時間数
- 延長時間(残業時間)数、休日労働時間数、深夜労働時間数
- 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
- 法第24条第1項の規定によって賃金の一部を控除した場合には、その額
なお、日日雇い入れられる者(1箇月を超えて引き続き使用される者を除く。)については、「賃金計算期間」を記入しなくてよい。
賃金台帳の保存期間および起算日
賃金台帳は、最後に記入された日から3年間保存することが必要です。
通達
(法第41条該当者の深夜割増賃金)
法第41条該当者については、施行規則において「労働時間数、延長時間(残業時間)数、休日労働時間数、深夜労働時間数」を記入しなくてよいとされているが、通達においては、深夜労働時間数は記入するように指導されています。(則54条、昭和23.2.3基発161号)
(組合専従者の賃金台帳)
組合に使用され、組合から賃金を受ける組合専従者の賃金台帳は、当該組合にも備えなければならない。(昭和24.11.9基収2747号)
(延長時間(残業時間)数、休日労働時間数、深夜労働時間数)
「延長時間(残業時間)数、休日労働時間数、深夜労働時間数」は、当該事業場の就業規則において労働基準法の規定と異なる所定労働時間又は休日の定めをした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数をもってこれに代えることができる。(則54条2項)
【例】1日の所定労働時間が7時間の場合は、その7時間を基に計算した残業時間を記入してよい。
(通貨以外のもので支払われる賃金)
「基本給、手当その他賃金の種類毎にその額」の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。(則54条3項)
(賃金の追給の場合の賃金台帳の記入法)
例えば、賃金の増額についての労使間の交渉が8月に決着し、4月に遡って賃金が増額されることになった場合に、4月から7月に支給した旧賃金との差額を8月に一括して支払ったとき、その追加額については各月に支払われたものとして平均賃金の計算を行うべきであるが、賃金台帳の記載に当たっては、過去4箇月分の賃金であることを明記して、8月分の賃金の種類による該当欄に記入する。(昭和22.11.5基発233号)
賃金台帳の整備にあたって注意すべきポイント
賃金台帳は、賃金の支払いのたびに必ず記入しなければなりません。賃金は毎月1回以上支払う必要があることから、賃金台帳も毎月1回以上記入することが必要です。
また、賃金台帳の記入にあたっては労働時間数を正確に管理することが必要不可欠であり、時間外労働や休日労動、深夜労動の時間数もそれぞれ明確にしなくてはなりません。
日日雇い入れられる者については、労働者名簿の調整義務はないが、賃金台帳の調整義務はある。